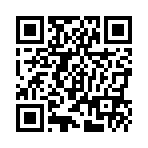2011年11月26日
MSR XGK Ⅱストーブ:実用編
以前に御紹介したMSRのXGKⅡストーブ、久し振りに出番がきました。
関連記事リンク

この手のタンク分離型のガソリンストーブは基本的にハードな登山や極地探検用と考えるべきで、色々な意味でファミリーキャンプには向いていません。
巷では故障が多いと言われるコールマンのガソリンストーブは、ポンプの注油位の簡単なメンテナンスだけで赤ガスを数十年使い続けてもノートラブルで使用出来る事も有る訳ですが、タンク分離型ストーブは定期的なメンテナンスが不可欠で、特にOリングが劣化すると使用中に加圧されたガソリンが噴き出し、火炎放射器となる可能性があります。
関連記事リンク
こいつは過去にポンプとボトルの接合部分から出火、運良くスノーキャンプだったのでストーブを雪で埋めて消火に成功しましたが、酸素を遮断しない限り、おそらく水を少々掛けた位では鎮火出来なかったでしょう。
更にMSRはポンプ部分が樹脂で、経年劣化でひび割れが発生する可能性もあります。
最近のMSRのポンプは強化繊維入りで強度UPしているようですが、こいつは90年代半ばに購入して既に20年近く前の物なので、使用前には入念なチェックが必要です。

いいかげん、新型を買ったら?って言われそうですが、最近の分離型ストーブ、あまり魅力的とは思えない訳ですよ。
MSRだと幅広い火力調整が出来るドラゴンフライの人気が高いようですが、XGKより火力調整機構が複雑になってOリングが増えている事を考えると、整備性がイマイチでは・・・?
他社の新型分離式は、ポンプが金属製なのは良いとしてもクイックカップリングとか、加圧インジゲーターとかの余計なギミックが多過ぎる。
多少使い勝手が上がったとしても、構造が複雑になり、故障(事故!)の可能性が高くなり、メンテナンスの手間が増える様な設計は個人的には間違いだと思っています。
まあ、昔と違って登山家はガソリンストーブなんて使わないし、極地探検家が沢山いる訳では無い。
商品として考えれば数が売れる一般キャンパー受けを狙うのは当然だと思いますが・・・
殆どのファミリーキャンパーの方々は、メンテを怠ると重大事故になる可能性もある機械だと言う事をあまり認識していないのではあるまいか?
再三このブログに書いてはいますが、室内でガソリンストーブを使うのは絶対に止めて下さい。
まあ、人から何を言われようが、実際に事故が発生しない限り『自分は大丈夫!』って人が多いんでしょうけれど。
さて、XGKⅡですが、最期に使ったのは2001年の小笠原諸島。
丁度10年使っていませんでした。
小笠原では2週間程、毎日海岸で昼食を作るのに使用。
母島は勿論、父島でも市街地をちょっと離れると店舗が無かったので、釣りの合間にインスタントラーメンを食べていました。
先日世界遺産に指定されたけれど、無垢な自然が手垢だらけにされてしまわなければ良いのですが・・・
例に寄って、購入してから赤ガスしか使った事はありません。
これは本体購入と同時にREIで購入したメンテナンスキットです。

最近のメンテナンスキットは小洒落た赤い専用BOXに収納されている様ですが、昔はビニール袋に無造作に入っていただけでした。
知人から貰った海外旅行土産の小さな紅茶の缶に収納してあります。
Oリング各種と予備ジェットなど。

まずはポンプカップのチェック。
工具無しで分解出来ます。

最近のMSRのカップは樹脂製のようですが、昔の物は皮製。
専用オイルを塗布。

取敢えず一度組み立ててからポンプで加圧、バルブを閉めたまましばらく放置します。
案の定?タンクとポンプの接合部分からガソリン洩れ・・・この状態で気が付かずに点火していたら確実に引火します。

ポンプとタンク接合部のOリングは力任せに幾らでも締め込む事が出来るので、結果として変形量が大きくなる。
ポンプをタンクにねじ込んだままにしていると、短期間で劣化する可能性が有ります。
タンクからポンプを外しておくと、小さな燃料フィルターが吸入パイプから外れて行方不明になるしねぇ・・・
こいつはヒビだらけでした。

まあ、10年前のOリングなんで当然・・・とも思えますが、昔のSIGGボトルのワッシャー型パッキンは10年以上使っても問題無い耐久性があったからねぇ・・・
この部分だけでもワッシャー型パッキンにすれば、飛躍的に安全性が高くなるような気がするのだが。
こいつは当然交換ですが、ついでに他の部分もチェックしておきますか。
バーナーの燃料パイプとポンプの接合部のOリングを抑えている樹脂パーツを専用工具で外します。

Oリングを取り出す。

燃料パイプを抜き差しするので細かな傷が付き易い場所です。
ヒビや劣化は見られませんが、新品に交換。
燃料バルブを取り外す。

うーん、このOリングはサイズが違うんだよな・・・スペアが無い。
燃料パイプのOリングと共用にすれば良いのに。
一応洩れは無さそうなのでそのまま組直す。
チェックバルブを分解、確認後組み立て。

バーナーカップを塞いでいるフレームスプレッダーを外します。
裏面はススで真黒。

ちなみに左側にあるのは90年代に購入したリペアキットに入っていた新品。
裏面に大量にススが付いていると炎が綺麗に広がらない事も有る様なので擦り落とします。

こんなモノで良いか・・・
専用工具かマイナスドライバーを使ってジェットを外します。

こいつの後継モデルは本体を上下に振るとジェットのノズルクリーニングをしてくれるギミックが付いているのですが、こいつは針金でジェットの穴をほじくるタイプ。
アルミの取っ手に針金が付いた専用工具を使用。

こんな感じで貫通させます。

古い単車のキャブレターをオーバーホールした事の有る方は判ると思いますが、この方法だと繊細なジェットの穴に傷を付け易いので注意が必要です。
頑固な汚れで無ければ釣り用ナイロン糸の使用がベター。
元通りに組直してチェック終了。
取敢えず常温では問題は無さそうだが、点火すると内圧が上がり、熱膨張で思わぬ所からのガソリン噴出も考えられるので油断は禁物。
例え新品のOリングを使ってメンテナンスしても、組み付け不良や組み立て時に傷が発生する可能性もあるし、ポンプとタンクが使用中に緩んでガソリンが噴出、大火傷で重傷を負った例もあるらしい・・・
さて、点火してみますか。
小型のボトルに燃料が定量一杯迄入っているので内部の空気量は少ない。
ポンピングは5回程で充分。
最近オプティマスの88ハイカーを使っている為に、数十回もポンピングしなければならないコールマンを使うのが面倒になってきた・・・加圧ポンプ付きプレヒート型ストーブが慣れれば一番使い勝手が良いと思う。
関連記事リンク
使い勝手と言えば、最近見た国産新型タンク分離型ガソリンストーブ。
小さな燃料バルブに、更に小さな文字が細々と書いてある。
夕闇せまる薄暗いキャンプ場、老眼気味のオッサンが泥酔状態で使う事は全く考慮されていない。
その点XGKの操作は簡単明瞭。
燃料バルブをオープン、バーナー部分がガソリンで黒く湿ったらバルブを締める。
点火。

今回は地面に芝生が無いので直置きしていますが、今時のキャンプ場では緑の絨毯に焼け焦げを作る事になるので使う場所を選ぶストーブです。
燃料パイプ内に残った燃料が熱せられてノズルから噴き出し始めたら燃料バルブをゆっくり開けて行きます。

123Rは未だ使い慣れていない為もあって、プレヒート不足で点火しない場合もありますが、こいつはバーナー周りの円筒形風避けとバーナー底部に効果的に配置されたウイックのお陰で着火ミスは皆無。
実は今回MSRを持ち出したのは、古い赤ガスを処分したかったんですよ。
昨年、今年と出撃の機会の無かった2馬力船外機の中に赤ガスを入れたまま放置してあったのですが、流石に車のガソリンタンクに戻すのも如何な物かと・・・
関連記事リンク
まあ、大型コッフェルで鍋をやると言う事も有り、普通だったらクラッシックを使うのですが、2年物の赤ガスは育ちの良いコールマンの口には合わないだろうと思い、悪喰?のXGKを引っ張り出してきた訳です。
全く何の問題も無く燃焼しています。

バーナー部の地色はゴールドなのですが、ススで黒いのは昔から。
ちなみに123Rでもビンテージ赤ガスを使ってみましたがススが大量発生、赤火が収まらない。

しばらく使っているうちに燃料が残った状態で自然鎮火・・・ノズルが詰まったようですな。
その点XGKは、一試合完全燃焼!!!(アストロ球団風に)・・・流石に極地用と言うべきか。

123Rと異なり、独立した極太ジェネレーターが付いているので粗悪な燃料でも完全燃焼するようです。
万一ジェネレーターが詰まった時には、ジェネレーター内部に収納されたワイヤーを抜いてメンテナンスが可能なので、コールマンの様に予備のジェネレーターを持ち歩く必要はありません。

設計は古くとも、複雑な構造でギミック満載の現行タンク分離型ストーブよりも基本性能は優れているのではあるまいか?
現在はあまり出番がありませんが、1カ月以上離島を含む長期ツーリングに行く事があれば、スペアのOリングを用意して、こいつを持って行く事になるでしょう。
今迄に国内の主な離島は大体行ってますが、離島へのガソリン輸送はドラム缶に入れてフェリーで搬送します。
ガソリンは長期保管され、水分が混入し、場合によっては細かな砂やゴミ、ドラム缶の錆が混入している可能性もあります。
まあ、そんな粗悪ガソリンばかりだったら、ストーブより先に単車のエンジンが不調になると思いますが、以前コールマンの550Bが不調になったのは長期滞在中の石垣島の海岸でした。
西表島や与那国島の海岸で、毎日飯を炊いていた頑丈なGIストーブのタンクが錆でやられたのも事実です。
関連記事リンク
補修用Oリング購入ついでに、多少火力調整が可能になっていると言う新型ポンプを買ってみようか・・・
関連記事リンク
後はゴトクがもう少ししっかりしていれば・・・
新型XGKのゴトクが移植できれば言う事は無いのだが。
関連記事リンク
2008/02/23

この手のタンク分離型のガソリンストーブは基本的にハードな登山や極地探検用と考えるべきで、色々な意味でファミリーキャンプには向いていません。
巷では故障が多いと言われるコールマンのガソリンストーブは、ポンプの注油位の簡単なメンテナンスだけで赤ガスを数十年使い続けてもノートラブルで使用出来る事も有る訳ですが、タンク分離型ストーブは定期的なメンテナンスが不可欠で、特にOリングが劣化すると使用中に加圧されたガソリンが噴き出し、火炎放射器となる可能性があります。
関連記事リンク
2008/02/02
こいつは過去にポンプとボトルの接合部分から出火、運良くスノーキャンプだったのでストーブを雪で埋めて消火に成功しましたが、酸素を遮断しない限り、おそらく水を少々掛けた位では鎮火出来なかったでしょう。
更にMSRはポンプ部分が樹脂で、経年劣化でひび割れが発生する可能性もあります。
最近のMSRのポンプは強化繊維入りで強度UPしているようですが、こいつは90年代半ばに購入して既に20年近く前の物なので、使用前には入念なチェックが必要です。

いいかげん、新型を買ったら?って言われそうですが、最近の分離型ストーブ、あまり魅力的とは思えない訳ですよ。
MSRだと幅広い火力調整が出来るドラゴンフライの人気が高いようですが、XGKより火力調整機構が複雑になってOリングが増えている事を考えると、整備性がイマイチでは・・・?
他社の新型分離式は、ポンプが金属製なのは良いとしてもクイックカップリングとか、加圧インジゲーターとかの余計なギミックが多過ぎる。
多少使い勝手が上がったとしても、構造が複雑になり、故障(事故!)の可能性が高くなり、メンテナンスの手間が増える様な設計は個人的には間違いだと思っています。
まあ、昔と違って登山家はガソリンストーブなんて使わないし、極地探検家が沢山いる訳では無い。
商品として考えれば数が売れる一般キャンパー受けを狙うのは当然だと思いますが・・・
殆どのファミリーキャンパーの方々は、メンテを怠ると重大事故になる可能性もある機械だと言う事をあまり認識していないのではあるまいか?
再三このブログに書いてはいますが、室内でガソリンストーブを使うのは絶対に止めて下さい。
まあ、人から何を言われようが、実際に事故が発生しない限り『自分は大丈夫!』って人が多いんでしょうけれど。
さて、XGKⅡですが、最期に使ったのは2001年の小笠原諸島。
丁度10年使っていませんでした。
小笠原では2週間程、毎日海岸で昼食を作るのに使用。
母島は勿論、父島でも市街地をちょっと離れると店舗が無かったので、釣りの合間にインスタントラーメンを食べていました。
先日世界遺産に指定されたけれど、無垢な自然が手垢だらけにされてしまわなければ良いのですが・・・
例に寄って、購入してから赤ガスしか使った事はありません。
これは本体購入と同時にREIで購入したメンテナンスキットです。

最近のメンテナンスキットは小洒落た赤い専用BOXに収納されている様ですが、昔はビニール袋に無造作に入っていただけでした。
知人から貰った海外旅行土産の小さな紅茶の缶に収納してあります。
Oリング各種と予備ジェットなど。

まずはポンプカップのチェック。
工具無しで分解出来ます。

最近のMSRのカップは樹脂製のようですが、昔の物は皮製。
専用オイルを塗布。

取敢えず一度組み立ててからポンプで加圧、バルブを閉めたまましばらく放置します。
案の定?タンクとポンプの接合部分からガソリン洩れ・・・この状態で気が付かずに点火していたら確実に引火します。

ポンプとタンク接合部のOリングは力任せに幾らでも締め込む事が出来るので、結果として変形量が大きくなる。
ポンプをタンクにねじ込んだままにしていると、短期間で劣化する可能性が有ります。
タンクからポンプを外しておくと、小さな燃料フィルターが吸入パイプから外れて行方不明になるしねぇ・・・
こいつはヒビだらけでした。

まあ、10年前のOリングなんで当然・・・とも思えますが、昔のSIGGボトルのワッシャー型パッキンは10年以上使っても問題無い耐久性があったからねぇ・・・
この部分だけでもワッシャー型パッキンにすれば、飛躍的に安全性が高くなるような気がするのだが。
こいつは当然交換ですが、ついでに他の部分もチェックしておきますか。
バーナーの燃料パイプとポンプの接合部のOリングを抑えている樹脂パーツを専用工具で外します。

Oリングを取り出す。

燃料パイプを抜き差しするので細かな傷が付き易い場所です。
ヒビや劣化は見られませんが、新品に交換。
燃料バルブを取り外す。

うーん、このOリングはサイズが違うんだよな・・・スペアが無い。
燃料パイプのOリングと共用にすれば良いのに。
一応洩れは無さそうなのでそのまま組直す。
チェックバルブを分解、確認後組み立て。

バーナーカップを塞いでいるフレームスプレッダーを外します。
裏面はススで真黒。

ちなみに左側にあるのは90年代に購入したリペアキットに入っていた新品。
裏面に大量にススが付いていると炎が綺麗に広がらない事も有る様なので擦り落とします。

こんなモノで良いか・・・
専用工具かマイナスドライバーを使ってジェットを外します。

こいつの後継モデルは本体を上下に振るとジェットのノズルクリーニングをしてくれるギミックが付いているのですが、こいつは針金でジェットの穴をほじくるタイプ。
アルミの取っ手に針金が付いた専用工具を使用。

こんな感じで貫通させます。

古い単車のキャブレターをオーバーホールした事の有る方は判ると思いますが、この方法だと繊細なジェットの穴に傷を付け易いので注意が必要です。
頑固な汚れで無ければ釣り用ナイロン糸の使用がベター。
元通りに組直してチェック終了。
取敢えず常温では問題は無さそうだが、点火すると内圧が上がり、熱膨張で思わぬ所からのガソリン噴出も考えられるので油断は禁物。
例え新品のOリングを使ってメンテナンスしても、組み付け不良や組み立て時に傷が発生する可能性もあるし、ポンプとタンクが使用中に緩んでガソリンが噴出、大火傷で重傷を負った例もあるらしい・・・
さて、点火してみますか。
小型のボトルに燃料が定量一杯迄入っているので内部の空気量は少ない。
ポンピングは5回程で充分。
最近オプティマスの88ハイカーを使っている為に、数十回もポンピングしなければならないコールマンを使うのが面倒になってきた・・・加圧ポンプ付きプレヒート型ストーブが慣れれば一番使い勝手が良いと思う。
関連記事リンク
2011/10/02
使い勝手と言えば、最近見た国産新型タンク分離型ガソリンストーブ。
小さな燃料バルブに、更に小さな文字が細々と書いてある。
夕闇せまる薄暗いキャンプ場、老眼気味のオッサンが泥酔状態で使う事は全く考慮されていない。
その点XGKの操作は簡単明瞭。
燃料バルブをオープン、バーナー部分がガソリンで黒く湿ったらバルブを締める。
点火。

今回は地面に芝生が無いので直置きしていますが、今時のキャンプ場では緑の絨毯に焼け焦げを作る事になるので使う場所を選ぶストーブです。
燃料パイプ内に残った燃料が熱せられてノズルから噴き出し始めたら燃料バルブをゆっくり開けて行きます。

123Rは未だ使い慣れていない為もあって、プレヒート不足で点火しない場合もありますが、こいつはバーナー周りの円筒形風避けとバーナー底部に効果的に配置されたウイックのお陰で着火ミスは皆無。
実は今回MSRを持ち出したのは、古い赤ガスを処分したかったんですよ。
昨年、今年と出撃の機会の無かった2馬力船外機の中に赤ガスを入れたまま放置してあったのですが、流石に車のガソリンタンクに戻すのも如何な物かと・・・
関連記事リンク
2008/04/29
まあ、大型コッフェルで鍋をやると言う事も有り、普通だったらクラッシックを使うのですが、2年物の赤ガスは育ちの良いコールマンの口には合わないだろうと思い、悪喰?のXGKを引っ張り出してきた訳です。
全く何の問題も無く燃焼しています。

バーナー部の地色はゴールドなのですが、ススで黒いのは昔から。
ちなみに123Rでもビンテージ赤ガスを使ってみましたがススが大量発生、赤火が収まらない。

しばらく使っているうちに燃料が残った状態で自然鎮火・・・ノズルが詰まったようですな。
その点XGKは、一試合完全燃焼!!!(アストロ球団風に)・・・流石に極地用と言うべきか。

123Rと異なり、独立した極太ジェネレーターが付いているので粗悪な燃料でも完全燃焼するようです。
万一ジェネレーターが詰まった時には、ジェネレーター内部に収納されたワイヤーを抜いてメンテナンスが可能なので、コールマンの様に予備のジェネレーターを持ち歩く必要はありません。

設計は古くとも、複雑な構造でギミック満載の現行タンク分離型ストーブよりも基本性能は優れているのではあるまいか?
現在はあまり出番がありませんが、1カ月以上離島を含む長期ツーリングに行く事があれば、スペアのOリングを用意して、こいつを持って行く事になるでしょう。
今迄に国内の主な離島は大体行ってますが、離島へのガソリン輸送はドラム缶に入れてフェリーで搬送します。
ガソリンは長期保管され、水分が混入し、場合によっては細かな砂やゴミ、ドラム缶の錆が混入している可能性もあります。
まあ、そんな粗悪ガソリンばかりだったら、ストーブより先に単車のエンジンが不調になると思いますが、以前コールマンの550Bが不調になったのは長期滞在中の石垣島の海岸でした。
西表島や与那国島の海岸で、毎日飯を炊いていた頑丈なGIストーブのタンクが錆でやられたのも事実です。
関連記事リンク
2009/11/07
2009/11/08
補修用Oリング購入ついでに、多少火力調整が可能になっていると言う新型ポンプを買ってみようか・・・
関連記事リンク
2012/12/01
後はゴトクがもう少ししっかりしていれば・・・
新型XGKのゴトクが移植できれば言う事は無いのだが。