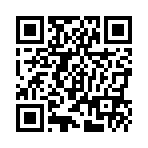2013年05月25日
コールマン ラウンドスクリーン2ルームハウス:改造編
昨年から使い始めたコールマンのラウンドスクリーン2ルームハウス、ゴールデンウィーク前に少々手を入れました。

関連記事リンク:コールマン ラウンドスクリーン2ルームハウス
●サイズ:約320×230×170(h)cm(インナーテント)、約320×270×170(h)cm(タープ)
●収納時サイズ:約φ28×82cm
●重量:約20kg
●フライ材質:75Dポリエステルタフタ(UVPRO、PU防水、シームシール)
●インナー材質:68Dポリエステルタフタ(撥水加工)
●フロア材質:210Dポリエステルオックス(PU防水、シームシール)
●ポール材質:FRP約φ12.5mm(ルーフ)
●スチール:約φ19mm(レッグ)
●FRP:約φ11mm(サイド)スチールφ19mm、長さ約180cm(キャノピー)
●耐水圧:約2、000mm(フロア2、000mm)
●定員:4~5人用
●仕様:キャノピー、前室、メッシュドア×2、ストームガード、ベンチレーション、ランタンハンガー、メッシュポケット、ギアハンモック
●付属品:キャノピーポール×2、ペグ、ロープ、ハンマー、キャリーバッグ
メーカー品番170T14150J
まずは前回撤収中に切れたポールのショックコードを交換するか・・・

関連記事リンク:コールマン純正ポールリペアショックコード
関連記事リンク:GLOCK(グロック)26
道具を揃えてショックコードをチェックすると、程良く伸びて問題無さそう・・・うーん、交換しなくて良いか。
それでは本題。
個人的にラウンドスクリーン2ルームハウスの最大の欠点だと思うのは、テント側のフライシートの裾が短い事。

地面との間にかなり広い隙間ができるので、冷たい風や雨、嫌な吸血昆虫や食事に特攻してくる蛾が入り放題・・・
ラウンドスクリーン2ルームハウスを購入したので廃棄する事にした、昔のスクリーンタープの裾を切り取って延長してみました。
関連記事リンク:コールマン3Pole Screen Tarp
まずは古いスクリーンタープに軽くアイロンを掛けてシワ取り。

裾の部分を、巾40cmでカット。
ハサミで切ると切断部がほつれてくるので、半田ゴテで切断。

ナイロン生地にナイロン糸なので簡単にカットできて後処理不要。
後は縫い付けるだけ・・・まあ、結構時間が掛ったけれど。
出来上がり。

流石純正。

コールマンのロゴが入っている事もあり、一見延長しているようには見えません。
強風と雨の翌日。

風に煽られると裾が内側に巻き込まれるが、40cmの長さがあるので雨の進入ははしっかり防いでいます。


延長部に元々ハトメが付いているので広げて固定も可。

ちなみに強風時はタープ上部の黄色と黒のポールのジョイント部分に予備のロープを通してペグダウンしておくと風に煽られ難い。

最期におまけ。
インナーテントをぶら下げているリングの付け根が切れた・・・

テント入り口の立ち上がりにうっかり体重を掛けた為ですが、洗濯済みの食器をカゴに入れてぶら下げたりもしていたので疲労もあったのではないかと思う。
ロープで吊ってみたが・・・修理するか。

常備してあるソーイングキットを取り出す。

関連記事リンク:レザーマン ウイングマン
取敢えず修理完了。

タープ内に小物をぶら下げる場所が全く無いんで不便なんだよね・・・ついついここにぶら下げてしまう。

何か細工するかなぁ?
関連記事リンク
関連記事リンク

関連記事リンク:コールマン ラウンドスクリーン2ルームハウス
●サイズ:約320×230×170(h)cm(インナーテント)、約320×270×170(h)cm(タープ)
●収納時サイズ:約φ28×82cm
●重量:約20kg
●フライ材質:75Dポリエステルタフタ(UVPRO、PU防水、シームシール)
●インナー材質:68Dポリエステルタフタ(撥水加工)
●フロア材質:210Dポリエステルオックス(PU防水、シームシール)
●ポール材質:FRP約φ12.5mm(ルーフ)
●スチール:約φ19mm(レッグ)
●FRP:約φ11mm(サイド)スチールφ19mm、長さ約180cm(キャノピー)
●耐水圧:約2、000mm(フロア2、000mm)
●定員:4~5人用
●仕様:キャノピー、前室、メッシュドア×2、ストームガード、ベンチレーション、ランタンハンガー、メッシュポケット、ギアハンモック
●付属品:キャノピーポール×2、ペグ、ロープ、ハンマー、キャリーバッグ
メーカー品番170T14150J
まずは前回撤収中に切れたポールのショックコードを交換するか・・・

関連記事リンク:コールマン純正ポールリペアショックコード
関連記事リンク:GLOCK(グロック)26
道具を揃えてショックコードをチェックすると、程良く伸びて問題無さそう・・・うーん、交換しなくて良いか。
それでは本題。
個人的にラウンドスクリーン2ルームハウスの最大の欠点だと思うのは、テント側のフライシートの裾が短い事。

地面との間にかなり広い隙間ができるので、冷たい風や雨、嫌な吸血昆虫や食事に特攻してくる蛾が入り放題・・・
ラウンドスクリーン2ルームハウスを購入したので廃棄する事にした、昔のスクリーンタープの裾を切り取って延長してみました。
関連記事リンク:コールマン3Pole Screen Tarp
まずは古いスクリーンタープに軽くアイロンを掛けてシワ取り。

裾の部分を、巾40cmでカット。
ハサミで切ると切断部がほつれてくるので、半田ゴテで切断。

ナイロン生地にナイロン糸なので簡単にカットできて後処理不要。
後は縫い付けるだけ・・・まあ、結構時間が掛ったけれど。
出来上がり。

流石純正。

コールマンのロゴが入っている事もあり、一見延長しているようには見えません。
強風と雨の翌日。

風に煽られると裾が内側に巻き込まれるが、40cmの長さがあるので雨の進入ははしっかり防いでいます。


延長部に元々ハトメが付いているので広げて固定も可。

ちなみに強風時はタープ上部の黄色と黒のポールのジョイント部分に予備のロープを通してペグダウンしておくと風に煽られ難い。

最期におまけ。
インナーテントをぶら下げているリングの付け根が切れた・・・

テント入り口の立ち上がりにうっかり体重を掛けた為ですが、洗濯済みの食器をカゴに入れてぶら下げたりもしていたので疲労もあったのではないかと思う。
ロープで吊ってみたが・・・修理するか。

常備してあるソーイングキットを取り出す。
関連記事リンク:レザーマン ウイングマン
取敢えず修理完了。

タープ内に小物をぶら下げる場所が全く無いんで不便なんだよね・・・ついついここにぶら下げてしまう。

何か細工するかなぁ?
関連記事リンク
2019/09/30
関連記事リンク
2016/10/22
2013年05月18日
野外飯:ホットケーキを焼く
ほろ酔い加減のおっさんでもできるキャンプ場の飯、今回は朝食編。
昔は知人が集まってのキャンプの朝は、前夜食べ切れなかった食材の処分大会でした。
朝からギトギトの『こてっちゃん』を山程食べさせられるとか・・・罰ゲームですな。
今朝はホットケーキを焼きます。

その昔、お子様用玩具のヒット商品に『ママレンジ』というのがありました。
参考リンク:ママレンジ(Wiki)
まま事用の小型コンロですが、本当のホットケーキが焼けるという画期的な物。
TVコマーシャルが繰り返し放映されていました。
子供でも出来る料理の代表作ですが、案外作った事が無いと言うおっさんも多いはず。
『マーマーレンジ ママレンジ・・・』鼻歌を歌いながら作るのが作法。
残念ながらキャンプ場だからエプロンは付けない。(CMソングを知らない人にはわからないか?)
袋の裏の作り方には卵と牛乳を入れるように書かれていますが、保存や運搬が大変なので使わない。

コッフェルに粉を少なめに入れます。
関連記事リンク:EPIクライマーズクッカー

最初から粉を大量に入れてしまうと、水を入れて固さ調整するのが困難です。

ダマにならないように掻き混ぜる。

フライパンを温める。
関連記事リンク:Coleman(コールマン)PEAK(ピーク)1

卵と牛乳を入れない代わりに、油ではなくバターを使用。

ちなみにキャンプ調理用の油は小分けで洩れ難い『日精 油っこくない炒め油 1/2ハーフ』が便利。
キャンプ用ストーブで粉物を焼く時は、少量ずつ何度かに分けて焼くと失敗が少ない。

蓋をしてしばらく放置。

表面が生乾きになり、細かな穴が開いてきます。

周りが焦げてきたらひっくり返す。

綺麗なキツネ色。

最終的な焼き上がりは中央を切って判断する。
関連記事リンク:コールドスチール マスターハンター サンマイ

シロップや蜂蜜なんかは当然持っていないのでバターをトッピング。

ホットケーキやお好み焼きなどの粉物はキャンプ向きの食糧です。
その時の空腹度や人数に合わせて適量を料理し、余ったら保存可能。
長期キャンプの際は非常食代わりに持参が吉。
昔は知人が集まってのキャンプの朝は、前夜食べ切れなかった食材の処分大会でした。
朝からギトギトの『こてっちゃん』を山程食べさせられるとか・・・罰ゲームですな。
今朝はホットケーキを焼きます。

その昔、お子様用玩具のヒット商品に『ママレンジ』というのがありました。
参考リンク:ママレンジ(Wiki)
まま事用の小型コンロですが、本当のホットケーキが焼けるという画期的な物。
TVコマーシャルが繰り返し放映されていました。
子供でも出来る料理の代表作ですが、案外作った事が無いと言うおっさんも多いはず。
『マーマーレンジ ママレンジ・・・』鼻歌を歌いながら作るのが作法。
残念ながらキャンプ場だからエプロンは付けない。(CMソングを知らない人にはわからないか?)
袋の裏の作り方には卵と牛乳を入れるように書かれていますが、保存や運搬が大変なので使わない。

コッフェルに粉を少なめに入れます。
関連記事リンク:EPIクライマーズクッカー

最初から粉を大量に入れてしまうと、水を入れて固さ調整するのが困難です。

ダマにならないように掻き混ぜる。

フライパンを温める。
関連記事リンク:Coleman(コールマン)PEAK(ピーク)1

卵と牛乳を入れない代わりに、油ではなくバターを使用。

ちなみにキャンプ調理用の油は小分けで洩れ難い『日精 油っこくない炒め油 1/2ハーフ』が便利。
キャンプ用ストーブで粉物を焼く時は、少量ずつ何度かに分けて焼くと失敗が少ない。

蓋をしてしばらく放置。

表面が生乾きになり、細かな穴が開いてきます。

周りが焦げてきたらひっくり返す。

綺麗なキツネ色。

最終的な焼き上がりは中央を切って判断する。
関連記事リンク:コールドスチール マスターハンター サンマイ

シロップや蜂蜜なんかは当然持っていないのでバターをトッピング。

ホットケーキやお好み焼きなどの粉物はキャンプ向きの食糧です。
その時の空腹度や人数に合わせて適量を料理し、余ったら保存可能。
長期キャンプの際は非常食代わりに持参が吉。
2013年05月17日
野外飯:サクラマスのちゃんちゃん焼き
今回作るのは北海道の代表的な郷土料理の一つ、ちゃんちゃん焼きです。
ちゃんちゃん焼きと言えば通常は鮭を使うのですが、今回はサクラマスを用意しました。

ちなみに鮭鱒だけでは無く、ホッケやアイナメ、黒ソイなどでもちゃんちゃん焼きをした事がありますが、簡単に出来て飯のおかずにも酒の肴にもなる野外向きメニューです。
念の為申し上げておきますが、ホッケの開きは使わないように・・・
全体を良く水で洗います。

普通は釣った魚を料理するのですが・・・

今回の北海道は連日風雨に悩まされ、小雪がちらつくしまつ・・・釣りどころでは無かった。
まあ、自然が相手なんで仕方が無いですな。
まずは肛門にナイフの切っ先を差し込み、鰓の下まで切り裂きます。

関連記事リンク:トップス トムブラウン(TOM BROWN) トラッカー(TRACKER) TBT-010
内臓を掻き出し、背骨沿いの血合いも指先で全て取り除きます。

ちなみに魚のアラや血合いはシンクに流さないように。
鰓の後ろ、片身を背骨迄切り込む。

まあ、このまま切り落としてしまっても良いのですが、頭の周りにも良いお肉が付いているので勿体無いですな。
アバラ骨を切り、開きにします。

一度に深く切り込まず、指先で身を開きながら少しずつ刃先を進めると上手く切れるはず。
鮭鱒は骨が細くて柔らかいので作業は楽ですな。
ホッケやソイはこのまま2枚に下ろして半身を刺身、残りをちゃんちゃん焼きにすると食卓が賑やかになります。
今回は小型の魚なのでフライパンで調理、まずはバターを溶かす。

関連記事リンク:オプティマス NO.88ハイカー プラス
キャンプ時はチューブ入りの物が便利。

皮を下にして魚を投入。

上にもバターを載せます。

味噌を投入。

ちなみに通常は白味噌を使う事が多いようですが、私の場合は赤味噌ですな。
日本酒がある時は日本酒で味噌を溶き、好みに寄って砂糖で甘みを付けます。
野菜は他の手持ちが無かったのでギョウジャニンニクを投入。
関連記事リンク:行者ニンニクの醤油漬け

蓋をして、蒸らせば完成。

これは以前に釣ったカラフトマスを調理した例。

大型魚は普通鉄板上で料理しますが、重くて嵩張るのでアルミフォイルを使う事が多い。

接岸したカラフトマスは脂っ気が抜けて淡泊なので、少々味付けを濃くした方が良いかも知れない。
変わったところでブラウントラウトのちゃんちゃん焼き。

これは自宅で調理中。

鮭鱒類では、今回調理したサクラマスが一番旨いかなぁ?
まあ、この時期北海道でちょっと大きなスーパーに行けばきれいに半身にしたサクラマスが売っているんでナイフなんて使わなくても調理できるんですが、魚を捌いた事が無い人は一度やってみた方が良いと思います。
切り身や加工食品ばかり食べていると、生き物から命を貰っているという実感が希薄になる気がするんですよね。
ちゃんちゃん焼きと言えば通常は鮭を使うのですが、今回はサクラマスを用意しました。

ちなみに鮭鱒だけでは無く、ホッケやアイナメ、黒ソイなどでもちゃんちゃん焼きをした事がありますが、簡単に出来て飯のおかずにも酒の肴にもなる野外向きメニューです。
念の為申し上げておきますが、ホッケの開きは使わないように・・・
全体を良く水で洗います。

普通は釣った魚を料理するのですが・・・

今回の北海道は連日風雨に悩まされ、小雪がちらつくしまつ・・・釣りどころでは無かった。
まあ、自然が相手なんで仕方が無いですな。
まずは肛門にナイフの切っ先を差し込み、鰓の下まで切り裂きます。

関連記事リンク:トップス トムブラウン(TOM BROWN) トラッカー(TRACKER) TBT-010
内臓を掻き出し、背骨沿いの血合いも指先で全て取り除きます。

ちなみに魚のアラや血合いはシンクに流さないように。
鰓の後ろ、片身を背骨迄切り込む。

まあ、このまま切り落としてしまっても良いのですが、頭の周りにも良いお肉が付いているので勿体無いですな。
アバラ骨を切り、開きにします。

一度に深く切り込まず、指先で身を開きながら少しずつ刃先を進めると上手く切れるはず。
鮭鱒は骨が細くて柔らかいので作業は楽ですな。
ホッケやソイはこのまま2枚に下ろして半身を刺身、残りをちゃんちゃん焼きにすると食卓が賑やかになります。
今回は小型の魚なのでフライパンで調理、まずはバターを溶かす。

関連記事リンク:オプティマス NO.88ハイカー プラス
キャンプ時はチューブ入りの物が便利。

皮を下にして魚を投入。

上にもバターを載せます。

味噌を投入。

ちなみに通常は白味噌を使う事が多いようですが、私の場合は赤味噌ですな。
日本酒がある時は日本酒で味噌を溶き、好みに寄って砂糖で甘みを付けます。
野菜は他の手持ちが無かったのでギョウジャニンニクを投入。
関連記事リンク:行者ニンニクの醤油漬け

蓋をして、蒸らせば完成。

これは以前に釣ったカラフトマスを調理した例。

大型魚は普通鉄板上で料理しますが、重くて嵩張るのでアルミフォイルを使う事が多い。

接岸したカラフトマスは脂っ気が抜けて淡泊なので、少々味付けを濃くした方が良いかも知れない。
変わったところでブラウントラウトのちゃんちゃん焼き。

これは自宅で調理中。

鮭鱒類では、今回調理したサクラマスが一番旨いかなぁ?
まあ、この時期北海道でちょっと大きなスーパーに行けばきれいに半身にしたサクラマスが売っているんでナイフなんて使わなくても調理できるんですが、魚を捌いた事が無い人は一度やってみた方が良いと思います。
切り身や加工食品ばかり食べていると、生き物から命を貰っているという実感が希薄になる気がするんですよね。
2013年05月16日
野外飯:行者ニンニクの醤油漬け
空気の良い野外で食べれば炊きたて御飯が何よりの御馳走ですが・・・
今回作るのは御飯の友にも酒の友にもなる万能オカズ。
春先に北海道や東北方面でポピュラーな山菜、行者ニンニクの醤油漬け。
参考リンク:ギョウジャニンニク(Wiki)
非常に簡単に作れて美味しいのでお試し下さい。
行者ニンニクは比較的簡単に採れる?山菜なので自生しているのを自分で採っても良いのですが、上記リンクのWikiの解説では収穫に時間が掛り、ほとんどの生息地は自然保護区・・・栽培物がスーパーや道の駅で安価に売っているので購入した物を使用しましょう。
関連記事リンク:山菜ガイドブック
価格は100円~300円位です。

まずは根元の赤いハカマの部分と、その下の白い薄皮を指で取り除きます。

特に葉の分岐部分を良く水洗いし、土や砂を洗い流します。

しばらく水切りします。
折り畳みのできるシリコン製のザルがあると便利。

5cm程度の長さに切る。

ちなみにアリシン等が含まれている為か、炭素鋼の刃物はあっという間に錆びるので注意。
関連記事リンク:トップス トムブラウン(TOM BROWN) トラッカー(TRACKER) TBT-010
タッパーに入れて醤油を多目に振りかける。

キャンプ用醤油はキッコーマンのいつでも新鮮シリーズが携行性に優れていて便利。
ガスが発生するので1日に一回は蓋を開いて中身を混ぜる事。
2~3日位経って葉がしんなりとしてきたら食べ頃。
浸かりが浅くても野菜炒めに混ぜれば美味。
一説には、食べ過ぎると眠れなくなりまっせ!と言うのだが、この時期キャンプ場ではAM4:00頃に鳥のさえずりで目覚めるのでPM9:00には酒を飲んでる事もあって熟睡。
ちなみに5月は他の様々な山菜も食べ頃。
キャンプ場だと天麩羅は大変なので、さっと茹でてマヨネーズで食べると良い。
灰汁抜きしなくても美味しいのはタラの芽とかコゴミですかねぇ?

ほろ苦い、春の味覚。
自分で山菜を収穫する人は、くれぐれも採り過ぎないようにお願いします。
腹一杯食べる物ではないと思うので・・・
今回作るのは御飯の友にも酒の友にもなる万能オカズ。
春先に北海道や東北方面でポピュラーな山菜、行者ニンニクの醤油漬け。
参考リンク:ギョウジャニンニク(Wiki)
非常に簡単に作れて美味しいのでお試し下さい。
行者ニンニクは比較的簡単に採れる?山菜なので自生しているのを自分で採っても良いのですが、上記リンクのWikiの解説では収穫に時間が掛り、ほとんどの生息地は自然保護区・・・栽培物がスーパーや道の駅で安価に売っているので購入した物を使用しましょう。
関連記事リンク:山菜ガイドブック
価格は100円~300円位です。

まずは根元の赤いハカマの部分と、その下の白い薄皮を指で取り除きます。

特に葉の分岐部分を良く水洗いし、土や砂を洗い流します。

しばらく水切りします。
折り畳みのできるシリコン製のザルがあると便利。

5cm程度の長さに切る。

ちなみにアリシン等が含まれている為か、炭素鋼の刃物はあっという間に錆びるので注意。
関連記事リンク:トップス トムブラウン(TOM BROWN) トラッカー(TRACKER) TBT-010
タッパーに入れて醤油を多目に振りかける。

キャンプ用醤油はキッコーマンのいつでも新鮮シリーズが携行性に優れていて便利。
ガスが発生するので1日に一回は蓋を開いて中身を混ぜる事。
2~3日位経って葉がしんなりとしてきたら食べ頃。
浸かりが浅くても野菜炒めに混ぜれば美味。
一説には、食べ過ぎると眠れなくなりまっせ!と言うのだが、この時期キャンプ場ではAM4:00頃に鳥のさえずりで目覚めるのでPM9:00には酒を飲んでる事もあって熟睡。
ちなみに5月は他の様々な山菜も食べ頃。
キャンプ場だと天麩羅は大変なので、さっと茹でてマヨネーズで食べると良い。
灰汁抜きしなくても美味しいのはタラの芽とかコゴミですかねぇ?

ほろ苦い、春の味覚。
自分で山菜を収穫する人は、くれぐれも採り過ぎないようにお願いします。
腹一杯食べる物ではないと思うので・・・
2013年05月15日
野外飯:米を炊く
このブログを御覧の方々はキャンプ場でどんな食事をされていますか?
書店に行くとキャンプ料理のレシピ本がずらずら並んでいる訳ですが、ダッジオーブンのような特殊器具を使ったり、自宅から仕込みをしなければならない料理は考えただけも面倒・・・
私の場合は基本的に食材は現地調達。
地物の新鮮な海産物や農産物は、あまり手を掛けるよりはそのまま焼いて食べるのが一番旨いので凝った料理を作った事はありません。
料理と言える程の物ではありませんが、おっさんでも作れるキャンプの食事について書いてみますか。
と、言う訳で第一回は米の炊き方です。
ちなみに自宅の炊飯器は一度も使った事が無いので炊飯器で米を炊く方法は知りません。
震災の計画停電の時にはカセットコンロを使ってコッフェルでお米を炊いていた・・・覚えておけば、いざという時にも役に立つはずです。
まずはお米の種類。
最近はキャンプ場では無洗米しか使いません。

マグカップで計量。
関連記事リンク:スノーピーク(snow peak) チタンダブルマグ450

大量の焼き牡蛎を食べる予定なので今夜は少な目に炊きます。
先日のゴールデンウィークには6泊7日の日程で大人2名で2kgを完食。
コッフェルはステンレスよりアルミ製がふっくら炊ける気がする。
関連記事リンク:エバニュー チロルクッカー40DX
コッフェルに米を入れたら倍の量の水を入れる。

次が一番重要な工程。
30分以上放置、充分に水を含ませる事。
これさえ守れば芯の有る焦げ飯は回避できます。
ストーブの火力は最初は全開。
沸騰したら吹きこぼれないように弱火にする。

コッフェルの蓋が持ちあがらないように重しをすると吉。
関連記事リンク:レザーマン ウイングマン

今回久々にピーク1ストーブを使ったが、やはり炊飯用としての使い勝手はピカ一。
関連記事リンク:Coleman(コールマン)PEAK(ピーク)1
123Rも悪くは無いが、タンクが加圧されると火力が上がるので目が離せない。
関連記事リンク:オプティマス スベア123R

まあ、一番使い勝手が良いのはカセットコンロですけどね。
炊き上がりは匂いで判断、ちょっと焦げ臭くなったら火を止める。
15分程放置して、蒸らした方が旨い。
コッフェルを逆さにしたり、底を薪で叩く必要はありません。
関連記事リンク:モリタ 飯盒
完成。

カニの穴が出来てます。
いわゆる薄皮一枚、底に軽く焦げが出来れば完璧。

ちなみに私はキャンプに板海苔を持って行きますが、コンパクトに収納可能で色々応用が効くので便利。
特に釣った魚でイクラ丼や海鮮丼を作る時には欠かせません。
まあ、御飯さえ上手く炊ければおかずは何でも良い位ですが。
書店に行くとキャンプ料理のレシピ本がずらずら並んでいる訳ですが、ダッジオーブンのような特殊器具を使ったり、自宅から仕込みをしなければならない料理は考えただけも面倒・・・
私の場合は基本的に食材は現地調達。
地物の新鮮な海産物や農産物は、あまり手を掛けるよりはそのまま焼いて食べるのが一番旨いので凝った料理を作った事はありません。
料理と言える程の物ではありませんが、おっさんでも作れるキャンプの食事について書いてみますか。
と、言う訳で第一回は米の炊き方です。
ちなみに自宅の炊飯器は一度も使った事が無いので炊飯器で米を炊く方法は知りません。
震災の計画停電の時にはカセットコンロを使ってコッフェルでお米を炊いていた・・・覚えておけば、いざという時にも役に立つはずです。
まずはお米の種類。
最近はキャンプ場では無洗米しか使いません。

マグカップで計量。
関連記事リンク:スノーピーク(snow peak) チタンダブルマグ450

大量の焼き牡蛎を食べる予定なので今夜は少な目に炊きます。
先日のゴールデンウィークには6泊7日の日程で大人2名で2kgを完食。
コッフェルはステンレスよりアルミ製がふっくら炊ける気がする。
関連記事リンク:エバニュー チロルクッカー40DX
コッフェルに米を入れたら倍の量の水を入れる。

次が一番重要な工程。
30分以上放置、充分に水を含ませる事。
これさえ守れば芯の有る焦げ飯は回避できます。
ストーブの火力は最初は全開。
沸騰したら吹きこぼれないように弱火にする。

コッフェルの蓋が持ちあがらないように重しをすると吉。
関連記事リンク:レザーマン ウイングマン

今回久々にピーク1ストーブを使ったが、やはり炊飯用としての使い勝手はピカ一。
関連記事リンク:Coleman(コールマン)PEAK(ピーク)1
123Rも悪くは無いが、タンクが加圧されると火力が上がるので目が離せない。
関連記事リンク:オプティマス スベア123R

まあ、一番使い勝手が良いのはカセットコンロですけどね。
炊き上がりは匂いで判断、ちょっと焦げ臭くなったら火を止める。
15分程放置して、蒸らした方が旨い。
コッフェルを逆さにしたり、底を薪で叩く必要はありません。
関連記事リンク:モリタ 飯盒
完成。

カニの穴が出来てます。
いわゆる薄皮一枚、底に軽く焦げが出来れば完璧。

ちなみに私はキャンプに板海苔を持って行きますが、コンパクトに収納可能で色々応用が効くので便利。
特に釣った魚でイクラ丼や海鮮丼を作る時には欠かせません。
まあ、御飯さえ上手く炊ければおかずは何でも良い位ですが。
2013年05月04日
北海道:歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)2013
歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)
宿泊日:2013年5月2~4日
住所:北海道寿都郡黒松内町字黒松内521-1
HP:歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)
https://www.lpic.utasai.jp/
-------------------------------------------------------
厚沢部を後にして日本海側を北上。
熊石近くの海岸で、立ち込んでルアーロッドを振る数人の釣り人を発見。

先日TV番組で有名キャスターがサクラマスを釣っていたポイントだった。
曇天だが風は比較的弱く、波も小さい。
車のルーフラックに積んだロッドケースからシーバスロッドを取り出し、ウェーダーを履いて入釣。
関連記事リンク:プラノ(PLANO)♯4588-00 ロッドケース
この時期ベイトはオオナゴらしいので細長いシルエットのメタルジグをチョイス。
海面に魚の跳ねは無いか、周囲の釣り人に釣れている気配は無いか・・・
粘っても釣れそうにないので短時間で撤収。
まあ、道内在住で専門に狙っている釣り師の方々でも簡単に釣れる魚では無いので、キャンプ旅の途中でホイホイ釣れる訳は無いのだが。
その後、ポイントガイドを参考に漁港を物色。
関連記事リンク:ここで釣れる北海道の港全ガイド
ホッケがかなり釣れている漁港を見つけて竿を出すが、コマセを使って浮き釣りをしている所にジグヘッドを投げ入れる訳には行かず、ちょっと離れてグラブを投げたが生き餌には勝てず・・・一度だけバイトが有ったが抜き上げ途中で落下。
前日にキャンプ場を予約してあるのだが、フリーサイトなのでチェックインを早目にしたいので釣りを切り上げて移動。
今回のキャンプ旅、最期にお世話になるのは歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)。
関連記事リンク:歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)
昨年も利用しているので今回は外すつもりだったのだが、これ以上北上すると雪の恐れがあるし、南方だとフェリーに乗る小樽が遠い。
首尾良く駐車場脇に設営。

関連記事リンク
連休中日、フリーサイトは3組程度で余裕があった。

ちなみにバンガローやカーサイトは予約で一杯でした。
直ぐ近くが管理棟で非常に便利。

ちなみに昨年気になった流し場のポンプの不具合は修理されたようだ。
フリーサイトの高台から場内を見た所。

真ん中が広場になっているのと、適当なアップダウンでカーサイトは良く見えません。

早朝、様々な鳥の声で目が覚めたが、キツツキのドラミングも聞こえる。
広場の梢に来ているようだ。

アカゲラでした。(正確にはエゾアカゲラ)
参考記事リンク:アカゲラ(Wiki)

関連記事リンク:FUJI(フジ) FINEPIX(ファインピックス) HS30EXR
ちなみに黒松内のカントリーサインは大型で頭が赤いクマゲラです。
参考記事リンク:クマゲラ(Wiki)
ちなみにこいつは翌朝もやって来たので、忍び寄ってもう少し大きな写真を撮ろうとしたが逃げられた・・・ドラミングを楽しんでいた他のキャンパーの方々には申し訳無い事をしました・・・
今年20周年らしいが、リピーターが多いのも納得。

温泉はキャンプ場近くの黒松内温泉ぶなの森。
参考リンク:黒松内温泉ぶなの森HP

ちなみに買い出しは黒松内市街地にAコープとセイコーマートはあるが品揃えはイマイチ・・・
日本海側の寿都町へ出て、海岸線の国道229号線をちょっと北上すると海産物の直売場がある。

昨年も購入したのですが、目的はカキ。

大振りのカキやホタテが格安・・・今回はカキ20個、ホタテ4個を購入しましたが、2人で食べるには正直多かった。

関連記事リンク:ロゴス ピラミッドグリル
ちなみに店内には見事なサクラマスも並んでいました・・・しかし、良い値段ですな。

買い出し後に島牧海岸に海アメマス狙いに行ったが、身を切るような冷たい逆風!

竿を出す気にもならない・・・
ルピック連泊後、小樽のビジネスホテルに移動。
昨年食べて感動した『なると』へ。
参考記事リンク:小樽 若鶏時代 なると HP

生ビールを飲みながら、目の前で揚げてくれるザンギ、手羽先、半身・・・変な寿司を喰うより余程満足度が高い。
残念ながら運河近くの支店は5月末で閉鎖されてしまうようです。
翌朝新潟行きフェリーで北海道を後に。

今回は天候に恵まれなかったが、次回は久々にカラフトマスを釣りに来たいねぇ。
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える長期移動型キャンプ装備
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ場の選び方
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ①北海道フェリー航路
宿泊日:2013年5月2~4日
住所:北海道寿都郡黒松内町字黒松内521-1
HP:歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)
https://www.lpic.utasai.jp/
-------------------------------------------------------
厚沢部を後にして日本海側を北上。
熊石近くの海岸で、立ち込んでルアーロッドを振る数人の釣り人を発見。

先日TV番組で有名キャスターがサクラマスを釣っていたポイントだった。
曇天だが風は比較的弱く、波も小さい。
車のルーフラックに積んだロッドケースからシーバスロッドを取り出し、ウェーダーを履いて入釣。
関連記事リンク:プラノ(PLANO)♯4588-00 ロッドケース
この時期ベイトはオオナゴらしいので細長いシルエットのメタルジグをチョイス。
海面に魚の跳ねは無いか、周囲の釣り人に釣れている気配は無いか・・・
粘っても釣れそうにないので短時間で撤収。
まあ、道内在住で専門に狙っている釣り師の方々でも簡単に釣れる魚では無いので、キャンプ旅の途中でホイホイ釣れる訳は無いのだが。
その後、ポイントガイドを参考に漁港を物色。
関連記事リンク:ここで釣れる北海道の港全ガイド
ホッケがかなり釣れている漁港を見つけて竿を出すが、コマセを使って浮き釣りをしている所にジグヘッドを投げ入れる訳には行かず、ちょっと離れてグラブを投げたが生き餌には勝てず・・・一度だけバイトが有ったが抜き上げ途中で落下。
前日にキャンプ場を予約してあるのだが、フリーサイトなのでチェックインを早目にしたいので釣りを切り上げて移動。
今回のキャンプ旅、最期にお世話になるのは歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)。
関連記事リンク:歌才オートキャンプ場L'PIC(ルピック)
昨年も利用しているので今回は外すつもりだったのだが、これ以上北上すると雪の恐れがあるし、南方だとフェリーに乗る小樽が遠い。
首尾良く駐車場脇に設営。

関連記事リンク
2012/05/12
連休中日、フリーサイトは3組程度で余裕があった。

ちなみにバンガローやカーサイトは予約で一杯でした。
直ぐ近くが管理棟で非常に便利。

ちなみに昨年気になった流し場のポンプの不具合は修理されたようだ。
フリーサイトの高台から場内を見た所。

真ん中が広場になっているのと、適当なアップダウンでカーサイトは良く見えません。

早朝、様々な鳥の声で目が覚めたが、キツツキのドラミングも聞こえる。
広場の梢に来ているようだ。

アカゲラでした。(正確にはエゾアカゲラ)
参考記事リンク:アカゲラ(Wiki)

関連記事リンク:FUJI(フジ) FINEPIX(ファインピックス) HS30EXR
ちなみに黒松内のカントリーサインは大型で頭が赤いクマゲラです。
参考記事リンク:クマゲラ(Wiki)
ちなみにこいつは翌朝もやって来たので、忍び寄ってもう少し大きな写真を撮ろうとしたが逃げられた・・・ドラミングを楽しんでいた他のキャンパーの方々には申し訳無い事をしました・・・
今年20周年らしいが、リピーターが多いのも納得。

温泉はキャンプ場近くの黒松内温泉ぶなの森。
参考リンク:黒松内温泉ぶなの森HP

ちなみに買い出しは黒松内市街地にAコープとセイコーマートはあるが品揃えはイマイチ・・・
日本海側の寿都町へ出て、海岸線の国道229号線をちょっと北上すると海産物の直売場がある。

昨年も購入したのですが、目的はカキ。

大振りのカキやホタテが格安・・・今回はカキ20個、ホタテ4個を購入しましたが、2人で食べるには正直多かった。

関連記事リンク:ロゴス ピラミッドグリル
ちなみに店内には見事なサクラマスも並んでいました・・・しかし、良い値段ですな。

買い出し後に島牧海岸に海アメマス狙いに行ったが、身を切るような冷たい逆風!

竿を出す気にもならない・・・
ルピック連泊後、小樽のビジネスホテルに移動。
昨年食べて感動した『なると』へ。
参考記事リンク:小樽 若鶏時代 なると HP

生ビールを飲みながら、目の前で揚げてくれるザンギ、手羽先、半身・・・変な寿司を喰うより余程満足度が高い。
残念ながら運河近くの支店は5月末で閉鎖されてしまうようです。
翌朝新潟行きフェリーで北海道を後に。

今回は天候に恵まれなかったが、次回は久々にカラフトマスを釣りに来たいねぇ。
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える長期移動型キャンプ装備
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ場の選び方
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ①北海道フェリー航路
2013年05月02日
北海道:鶉ダムオートキャンプ場ハチャムの森
鶉ダムオートキャンプ場ハチャムの森
住所:北海道桧山郡厚沢部町字木間内60番地の1
利用日:2013年4月30日~5月2日
参考リンク:厚沢部町 鶉ダムオートキャンプ場HP
------------------------------------------------------
小雨交じりの曇天、国道5号線を南下。
途中、長万部を通過。
久々に直売所で蟹でも買おうと思ったのだが、店の半分は閉鎖されていて非常に寂れていた・・・高速道路が開通して観光バスが素通り、観光客が激減したようだ。
何も買う気にならず、通過。
最初は八雲辺りのキャンプ場で一泊してから函館に向かう予定だったのだが、天気予報では海岸部は風が強いらしい・・・悪天候時にテントの設営、撤収をするのも面倒なので函館近くへ移動して連泊する事にした。
途中、八雲市街地外れのレストランで昼食。

参照リンク:スイスレストラン アルポンHP
スイス料理って言うのは初見です。
家人がネットで見つけたのだが、事前に調べてなければ絶対に行き付けない町外れの目立たないお店。
まずはチーズフォンデュ。

今回キャンプ場で食べる予定だったが、キャンプ場周囲のマーケットでは材料が入手できなかった。
溶かしたチーズにニンニクなどが入っていて美味い。
流石にプロの技。
家人オーダーのアスパラ入りスパゲティー。

この時期、地のアスパラは絶品ですな。
私がオーダーしたのはスペアリブ。

腹が一杯になったところで今夜の宿泊地の選定。
函館周辺のキャンプ場だと、真っ先に頭に浮かぶのが東大沼キャンプ場。
ロケーションが良い上に、未だに無料で開放されている人気キャンプ場だがGWなので混雑しているだろうと言う予測と、なるべくなら初見のキャンプ場に泊ってみたいと言う事で今回選んだのは函館と江差の中間にある鶉ダムオートキャンプ場。
山間部の谷沿いに位置するので悪天候に強いのではという期待もある。
ちなみに『鶉』という字は『うずら』と読みます。
キャンプ場に着くと他のキャンパーは皆無。
フリーサイトでも良かったのだが、谷沿いの電源付きサイトをチョイス。

関連記事リンク
このキャンプ場はあまりロケーションが良く無く、フリーサイトと電源無しサイトは横にダムサイト管理用?の道路が通っていて何だか落ち着かない。

今回は他のキャンパーが皆無だったから良かったがサイトの間隔も極端に狭く、ブラインドも全く無し。
自由に場所が選べたので一番広い施設横をキープできたが、煩雑時には来る気にならない。

キャンプ場全体が不自然な程平坦で、木々に葉が無い事もあるが端から端まで見通せる。

電源はテーブルとチェアの近くに設置されているが、配置がイマイチで使うにしてもどうやってテントやタープを配置するのか迷う?(全く使わなかったけど)

サイトの横にはダムの放水口からの流れ・・・釣りはできそうに無いね。

こちらはキャビン。

キャンプ場から見えるダムの放水口。

炊事場。

広い洗い場だが、驚いた事に御影石製だ。

こちらはトイレ。


洗面台も樹脂製のようだが御影石調でデザインされている。
個人的にはキャンプ場の設備で重要なのは清潔で機能的な事だと思っていて、豪華さは不要だと思うんですが・・・
多分、キャンプをやった事の無い人がキャンプ場を設計するとこんなキャンプ場が出来るのではないだろうか?
キャンプ場全体が人工的過ぎて味気無い・・・まあ、こんなキャンプ場が好きだっていう人もいるかも知れないけど。
位置的には観光や釣りには丁度良いのだが、何だが再訪しようという気にならない訳ですよ。
ちなみに周囲に買い出しできる所は殆ど無く、一番近いセイコーマートには買う気になる食材はG7ワインのみ。
温泉は3カ所ほどあって、初日は館地区憩いの家へ。
参考リンク:厚沢部町 館地区憩いの家HP
洗い場にシャンプーどころか石鹸も無いが、地元の方々が集うノンビリした湯。
翌日はうずら温泉。
参考リンク:厚沢部町 うずら温泉HP

こちらはレストラン併設のおしゃれ温泉でした。
悪天候で釣りは出来ず、取敢えず周辺の観光。
JRの森駅へ。

コンビニみたいな外観ですが・・・キオスクに行くと出来たてのイカ飯が入荷していました。

周囲の道の駅なんかで売っているのとは違って小振りのイカが入っています。

函館山で夜景でも・・・と思ったのだが天候が回復しないので久々に松前半島をドライブ。
松前の道の駅でマグロの漬け丼を食べる。

相変わらず天候は悪く、明日の夜は札幌周辺でも積雪との予報!
ニセコ周辺に移動する予定でしたがあまり北上するのは不味いなぁ・・・
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える長期移動型キャンプ装備
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ場の選び方
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ①北海道フェリー航路
住所:北海道桧山郡厚沢部町字木間内60番地の1
利用日:2013年4月30日~5月2日
参考リンク:厚沢部町 鶉ダムオートキャンプ場HP
------------------------------------------------------
小雨交じりの曇天、国道5号線を南下。
途中、長万部を通過。
久々に直売所で蟹でも買おうと思ったのだが、店の半分は閉鎖されていて非常に寂れていた・・・高速道路が開通して観光バスが素通り、観光客が激減したようだ。
何も買う気にならず、通過。
最初は八雲辺りのキャンプ場で一泊してから函館に向かう予定だったのだが、天気予報では海岸部は風が強いらしい・・・悪天候時にテントの設営、撤収をするのも面倒なので函館近くへ移動して連泊する事にした。
途中、八雲市街地外れのレストランで昼食。

参照リンク:スイスレストラン アルポンHP
スイス料理って言うのは初見です。
家人がネットで見つけたのだが、事前に調べてなければ絶対に行き付けない町外れの目立たないお店。
まずはチーズフォンデュ。

今回キャンプ場で食べる予定だったが、キャンプ場周囲のマーケットでは材料が入手できなかった。
溶かしたチーズにニンニクなどが入っていて美味い。
流石にプロの技。
家人オーダーのアスパラ入りスパゲティー。

この時期、地のアスパラは絶品ですな。
私がオーダーしたのはスペアリブ。

腹が一杯になったところで今夜の宿泊地の選定。
函館周辺のキャンプ場だと、真っ先に頭に浮かぶのが東大沼キャンプ場。
ロケーションが良い上に、未だに無料で開放されている人気キャンプ場だがGWなので混雑しているだろうと言う予測と、なるべくなら初見のキャンプ場に泊ってみたいと言う事で今回選んだのは函館と江差の中間にある鶉ダムオートキャンプ場。
山間部の谷沿いに位置するので悪天候に強いのではという期待もある。
ちなみに『鶉』という字は『うずら』と読みます。
キャンプ場に着くと他のキャンパーは皆無。
フリーサイトでも良かったのだが、谷沿いの電源付きサイトをチョイス。

関連記事リンク
2012/05/12
このキャンプ場はあまりロケーションが良く無く、フリーサイトと電源無しサイトは横にダムサイト管理用?の道路が通っていて何だか落ち着かない。

今回は他のキャンパーが皆無だったから良かったがサイトの間隔も極端に狭く、ブラインドも全く無し。
自由に場所が選べたので一番広い施設横をキープできたが、煩雑時には来る気にならない。

キャンプ場全体が不自然な程平坦で、木々に葉が無い事もあるが端から端まで見通せる。

電源はテーブルとチェアの近くに設置されているが、配置がイマイチで使うにしてもどうやってテントやタープを配置するのか迷う?(全く使わなかったけど)

サイトの横にはダムの放水口からの流れ・・・釣りはできそうに無いね。

こちらはキャビン。

キャンプ場から見えるダムの放水口。

炊事場。

広い洗い場だが、驚いた事に御影石製だ。

こちらはトイレ。


洗面台も樹脂製のようだが御影石調でデザインされている。
個人的にはキャンプ場の設備で重要なのは清潔で機能的な事だと思っていて、豪華さは不要だと思うんですが・・・
多分、キャンプをやった事の無い人がキャンプ場を設計するとこんなキャンプ場が出来るのではないだろうか?
キャンプ場全体が人工的過ぎて味気無い・・・まあ、こんなキャンプ場が好きだっていう人もいるかも知れないけど。
位置的には観光や釣りには丁度良いのだが、何だが再訪しようという気にならない訳ですよ。
ちなみに周囲に買い出しできる所は殆ど無く、一番近いセイコーマートには買う気になる食材はG7ワインのみ。
温泉は3カ所ほどあって、初日は館地区憩いの家へ。
参考リンク:厚沢部町 館地区憩いの家HP
洗い場にシャンプーどころか石鹸も無いが、地元の方々が集うノンビリした湯。
翌日はうずら温泉。
参考リンク:厚沢部町 うずら温泉HP

こちらはレストラン併設のおしゃれ温泉でした。
悪天候で釣りは出来ず、取敢えず周辺の観光。
JRの森駅へ。

コンビニみたいな外観ですが・・・キオスクに行くと出来たてのイカ飯が入荷していました。

周囲の道の駅なんかで売っているのとは違って小振りのイカが入っています。

函館山で夜景でも・・・と思ったのだが天候が回復しないので久々に松前半島をドライブ。
松前の道の駅でマグロの漬け丼を食べる。

相変わらず天候は悪く、明日の夜は札幌周辺でも積雪との予報!
ニセコ周辺に移動する予定でしたがあまり北上するのは不味いなぁ・・・
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える長期移動型キャンプ装備
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ場の選び方
YouTube:北海道キャンプ旅30回のヘビーリピーターが考える北海道キャンプ①北海道フェリー航路