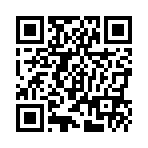2010年04月17日
ABU 506
今朝起きたら薄っすら雪が積もっていた・・・関東平野部で四月中旬に積雪なんて記憶に無いよ。
異常気象なのかねぇ?
今回紹介するのはリール界の異端児、ABU506です。

70年代購入。

当時、小型スピニングリールとしては以前紹介したミッチェル408を愛用していた訳ですが、湖用リールとしては少々小さい。
関連記事リンク
当時、中型スピニングリールとしてはミッチェルだと410、ABUならカーディナル44が定番でしたでしょうか。
関連記事リンク
そんな中、私のチョイスは当時もマイナーだったABU506。

カーディナルより、かなり安かったんですよね。
当時カーディナル44は2万円を超える価格だったと思いますが、こいつは1万円代中頃で購入できたのではないかと記憶しています。
スピンキャスティングリールの銘品、アブマチックの機構をそのままにスピニングタックルで使用できるようにした変則リールです。
関連記事リンク
購入当時は真っ赤なボディーにスタードラグの付いたABU505とか、一回り大型のABU507等、結構ラインナップが充実していたのですが現在は全て廃番。
長年愛用していますが、釣り場で同じ500系リールを使っている人を見た事が無い。
私が使っていると、他の釣り人にジロジロ見られる事が多かった。
ABUのリールはペットネームが付いていました。
ベイトキャスティングリールはアンバサダー。
スピニングリールはカーディナル。
スピンキャストリールはアブマチック。
フライリールはディプロマット。
関連記事リンク
ところがこのシーリーズだけはペットネームが無い・・・廉価版扱いだったのかなぁ?
PRODUCT OF SWEDEN

今回ブログを書くにあたってネットで検索してみると、結構ファンの方がいる模様。
一般的?には釣りキチ三平のイトウの原野に出てくる『湿原の怪人!谷地坊主』が使っていたリールと言った方が通りが良いかも知れません。
多分谷地坊主が使っていたのは506より一回り大型の507ではないかと思います。
通常500シリーズはスピニングリールと同じ様にリールの足を中指と薬指の間に挟んで使うのですが、谷地坊主はダブルハンドルのロッドと組み合わせてリール全体をパーミングして使っていました。

こんな持ち方ですね。

リールを握っただけでは保持が不完全なので、ダブルハンドルロッドの竿尻を肘で脇に挟みます。
ちなみに写真のロッドはフェンウイックのヒューチョと言うイトウ用。
関連記事リンク
LG89S M-2 HUCHOⅡ J

通常のスピニングリールだとベイルがあるのですが、ABU500シリーズは回転部分がカップ内部に収納されているのでリールを鷲掴みにしても問題無し。
指先一本でラインのリリースが可能なABU500シリーズでなければ出来ない技です。
実際にこの持ち方をすると判るのですが、リールの足とボディー後半の曲線が実に手に馴染む。

この握り方ではオーバーヘッドキャストをしようとすると脇が開いて竿尻が固定出来ません。
連載当時は漫画ならではの脚色かと思いました。
しかし実際に後年北海道の湿原でイトウ釣りをしてみて判ったのは、河畔にブッシュが密生しているので頭上に開いているスペースが無い。
河口近くでも無い限りアンダーハンドやサイドキャストを主に使うと言う事が判明。
矢口先生は入念な取材をされてから漫画化されていたようなので、おそらく当時の釧路湿原にはABU500シリーズを谷地坊主の様に操る達人が居たのでしょうな。
現在でもこれ程使い勝手の良いリールは他に見当たりません。
人差し指でリール前面の黒い部品を軽く押すだけでラインがフリーとなって自動的に人差し指にラインが掛かり、キャスティング準備完了。


サムバー無しのベイトキャスティングリールやスピニングリールは両手を使わないとキャスティングの準備が出来ない事を考えると圧倒的に操作が早い。
ロッド上部にリールをセットする一般的なクローズドフェースリールだとキャスト後のラインコントロールが困難だが、ABU500シリーズはキャスト後、指先を使っての微妙なラインコントロールが出来ます。
ベイルが無いのでスピニングリールよりコントロールは容易です。
一般的なスピニングリールだと、ハンドルの巻き始めにベールの戻りが重い事が有るが、506は巻き上げの初めが非常に軽いのも利点の一つ・・・まあ、それが欠点にもなるのだが。
ちなみに当時のミッチェルやカーディナルはリールを巻くと『カリ カリ カリ』とアンチリバースのラチェット音がするのだが、こいつは無音です。
ドラグはオートシンクロと言う特殊な物。

ハンドルを握っている限りはドラグが固定されてラインが出ない。
ハンドルを放すと、予め設定されたドラグ値でラインが出る。
ドラグ値は黒いノブで調整します。
ノブが小さいので魚とやり取りしている時は調整し難い。
ドラグは滑り初めの抵抗がちょっと大き目なので、弱目に設定する事が多いのですが、足元迄魚を寄せて口を掴もうと左手をハンドルから離すとドラグが緩むので注意が必要です。
こいつのもう一つの特徴はトラブルフリー。
ベイトキャスティングリールはバックラッシュ、スピニングリールは糸撚れと言うライントラブルが付きまとう物ですが、ABU500シリーズはバックラッシュしない事は勿論、スピニングの宿命と言える糸撚れも殆ど発生しません。
ローターとカバーの間をラインが通る時に適度な抵抗となって巻き取り時のラインがスプールから浮き難い。
スプールはハンドル回転に連動して前後に移動。

ラインが平行に巻かれてトラブルを減らします。

安いクローズドフェイスリールだと、この機能が省略されている事が多いのですが、ライントラブルが少ないと言う利点が台無しになってしまうので、購入時に考慮するポイントになるでしょう。
スピニングリールはドラグが働くとスプールが回転してラインが出ますが、ABU500シリーズはローターが逆回転してラインが出ます。
この点もラインの撚れが少ない原因になっているかも知れません。
スペアスプールと『へ』の字型の専用工具が付いていたのだが行方不明・・・
通常のメンテナンスが簡単なのも当時の欧州製リールの美点の一つ。
スプールカバーとローター、スプールの分解は工具不要で30秒もかからない。

ボディーのサイドプレートはネジ1本で開閉可能。

ネジ頭はローレット(頭の周りのギザギザ)加工してあるので、最初に工具を使って緩めれば指先で取り外せる。

カーディナル44同様、サイドカバーからネジが落下し難くなっている。

サイドカバー内側に刻印。

74年製のようです。
内部構造はシンプル。

使い方のコツとしては、ラインの管理が重要。

スプールに刻印がされていますが、ラインが多過ぎても少な過ぎてもトラブルの元。

スプールは細軸だが、コルクのエコノマイザーが標準で付属しています。
適合ラインは6ポンドか8ポンドのナイロンラインが最適だと思いますが、私は4~12ポンド迄使った実績があります。
ピックアップピンがステンレスなので、PEラインは摩耗するのではないかと思い、使った事はありません。

後はキャスト時にハンドルの位置が悪いとハンドルが自重で回転してピンが飛び出し、ルアーを水面に叩き付ける事になる。
この欠点はハンドルをベイトキャスティングリール用のダブルハンドルにして改善されているユーザーもいるようだ。
もっとも506はオートシンクロなのでドラグ用の突起があって、改造は難しそうだが。

弱点としてはやはり重量。

ギア比は低いのだがスプール径が大き目なので、渓流釣りでも使用可能。
手返しが早くてスピナーを多用してもライントラブルが少ないので渓流のルアー釣りには最適なリールの一つだが、やはり重過ぎる。
もう少し軽ければベストなのだが。
90年代迄はこいつと同系統のリールが売られていたのだが、現在は絶滅。

現在、ABUやフルーガー、シェークスピア等からスピンキャスティングリールを下向きにセッティングして、レバーでライン操作をするリールがリリースされている。
最新技術を盛り込んで、PEライン対応、小型軽量、指先で微妙なラインコントロールが出来る新生500シリーズをリリース希望。
糸フケが出易い釣り、例えばエギング用、特にナイトフィッシングには最適の一台となると思うのだが。
関連記事リンク
異常気象なのかねぇ?
今回紹介するのはリール界の異端児、ABU506です。

70年代購入。

当時、小型スピニングリールとしては以前紹介したミッチェル408を愛用していた訳ですが、湖用リールとしては少々小さい。
関連記事リンク
2010/04/03
当時、中型スピニングリールとしてはミッチェルだと410、ABUならカーディナル44が定番でしたでしょうか。
関連記事リンク
2010/04/10
そんな中、私のチョイスは当時もマイナーだったABU506。

カーディナルより、かなり安かったんですよね。
当時カーディナル44は2万円を超える価格だったと思いますが、こいつは1万円代中頃で購入できたのではないかと記憶しています。
スピンキャスティングリールの銘品、アブマチックの機構をそのままにスピニングタックルで使用できるようにした変則リールです。
関連記事リンク
2010/04/18
購入当時は真っ赤なボディーにスタードラグの付いたABU505とか、一回り大型のABU507等、結構ラインナップが充実していたのですが現在は全て廃番。
長年愛用していますが、釣り場で同じ500系リールを使っている人を見た事が無い。
私が使っていると、他の釣り人にジロジロ見られる事が多かった。
ABUのリールはペットネームが付いていました。
ベイトキャスティングリールはアンバサダー。
スピニングリールはカーディナル。
スピンキャストリールはアブマチック。
フライリールはディプロマット。
関連記事リンク
2010/03/20
2010/05/01
ところがこのシーリーズだけはペットネームが無い・・・廉価版扱いだったのかなぁ?
PRODUCT OF SWEDEN

今回ブログを書くにあたってネットで検索してみると、結構ファンの方がいる模様。
一般的?には釣りキチ三平のイトウの原野に出てくる『湿原の怪人!谷地坊主』が使っていたリールと言った方が通りが良いかも知れません。
多分谷地坊主が使っていたのは506より一回り大型の507ではないかと思います。
通常500シリーズはスピニングリールと同じ様にリールの足を中指と薬指の間に挟んで使うのですが、谷地坊主はダブルハンドルのロッドと組み合わせてリール全体をパーミングして使っていました。

こんな持ち方ですね。

リールを握っただけでは保持が不完全なので、ダブルハンドルロッドの竿尻を肘で脇に挟みます。
ちなみに写真のロッドはフェンウイックのヒューチョと言うイトウ用。
関連記事リンク
2011/08/20
LG89S M-2 HUCHOⅡ J

通常のスピニングリールだとベイルがあるのですが、ABU500シリーズは回転部分がカップ内部に収納されているのでリールを鷲掴みにしても問題無し。
指先一本でラインのリリースが可能なABU500シリーズでなければ出来ない技です。
実際にこの持ち方をすると判るのですが、リールの足とボディー後半の曲線が実に手に馴染む。

この握り方ではオーバーヘッドキャストをしようとすると脇が開いて竿尻が固定出来ません。
連載当時は漫画ならではの脚色かと思いました。
しかし実際に後年北海道の湿原でイトウ釣りをしてみて判ったのは、河畔にブッシュが密生しているので頭上に開いているスペースが無い。
河口近くでも無い限りアンダーハンドやサイドキャストを主に使うと言う事が判明。
矢口先生は入念な取材をされてから漫画化されていたようなので、おそらく当時の釧路湿原にはABU500シリーズを谷地坊主の様に操る達人が居たのでしょうな。
現在でもこれ程使い勝手の良いリールは他に見当たりません。
人差し指でリール前面の黒い部品を軽く押すだけでラインがフリーとなって自動的に人差し指にラインが掛かり、キャスティング準備完了。


サムバー無しのベイトキャスティングリールやスピニングリールは両手を使わないとキャスティングの準備が出来ない事を考えると圧倒的に操作が早い。
ロッド上部にリールをセットする一般的なクローズドフェースリールだとキャスト後のラインコントロールが困難だが、ABU500シリーズはキャスト後、指先を使っての微妙なラインコントロールが出来ます。
ベイルが無いのでスピニングリールよりコントロールは容易です。
一般的なスピニングリールだと、ハンドルの巻き始めにベールの戻りが重い事が有るが、506は巻き上げの初めが非常に軽いのも利点の一つ・・・まあ、それが欠点にもなるのだが。
ちなみに当時のミッチェルやカーディナルはリールを巻くと『カリ カリ カリ』とアンチリバースのラチェット音がするのだが、こいつは無音です。
ドラグはオートシンクロと言う特殊な物。

ハンドルを握っている限りはドラグが固定されてラインが出ない。
ハンドルを放すと、予め設定されたドラグ値でラインが出る。
ドラグ値は黒いノブで調整します。
ノブが小さいので魚とやり取りしている時は調整し難い。
ドラグは滑り初めの抵抗がちょっと大き目なので、弱目に設定する事が多いのですが、足元迄魚を寄せて口を掴もうと左手をハンドルから離すとドラグが緩むので注意が必要です。
こいつのもう一つの特徴はトラブルフリー。
ベイトキャスティングリールはバックラッシュ、スピニングリールは糸撚れと言うライントラブルが付きまとう物ですが、ABU500シリーズはバックラッシュしない事は勿論、スピニングの宿命と言える糸撚れも殆ど発生しません。
ローターとカバーの間をラインが通る時に適度な抵抗となって巻き取り時のラインがスプールから浮き難い。
スプールはハンドル回転に連動して前後に移動。

ラインが平行に巻かれてトラブルを減らします。

安いクローズドフェイスリールだと、この機能が省略されている事が多いのですが、ライントラブルが少ないと言う利点が台無しになってしまうので、購入時に考慮するポイントになるでしょう。
スピニングリールはドラグが働くとスプールが回転してラインが出ますが、ABU500シリーズはローターが逆回転してラインが出ます。
この点もラインの撚れが少ない原因になっているかも知れません。
スペアスプールと『へ』の字型の専用工具が付いていたのだが行方不明・・・
通常のメンテナンスが簡単なのも当時の欧州製リールの美点の一つ。
スプールカバーとローター、スプールの分解は工具不要で30秒もかからない。

ボディーのサイドプレートはネジ1本で開閉可能。

ネジ頭はローレット(頭の周りのギザギザ)加工してあるので、最初に工具を使って緩めれば指先で取り外せる。

カーディナル44同様、サイドカバーからネジが落下し難くなっている。

サイドカバー内側に刻印。

74年製のようです。
内部構造はシンプル。

使い方のコツとしては、ラインの管理が重要。

スプールに刻印がされていますが、ラインが多過ぎても少な過ぎてもトラブルの元。

スプールは細軸だが、コルクのエコノマイザーが標準で付属しています。
適合ラインは6ポンドか8ポンドのナイロンラインが最適だと思いますが、私は4~12ポンド迄使った実績があります。
ピックアップピンがステンレスなので、PEラインは摩耗するのではないかと思い、使った事はありません。

後はキャスト時にハンドルの位置が悪いとハンドルが自重で回転してピンが飛び出し、ルアーを水面に叩き付ける事になる。
この欠点はハンドルをベイトキャスティングリール用のダブルハンドルにして改善されているユーザーもいるようだ。
もっとも506はオートシンクロなのでドラグ用の突起があって、改造は難しそうだが。

弱点としてはやはり重量。

ギア比は低いのだがスプール径が大き目なので、渓流釣りでも使用可能。
手返しが早くてスピナーを多用してもライントラブルが少ないので渓流のルアー釣りには最適なリールの一つだが、やはり重過ぎる。
もう少し軽ければベストなのだが。
90年代迄はこいつと同系統のリールが売られていたのだが、現在は絶滅。

現在、ABUやフルーガー、シェークスピア等からスピンキャスティングリールを下向きにセッティングして、レバーでライン操作をするリールがリリースされている。
最新技術を盛り込んで、PEライン対応、小型軽量、指先で微妙なラインコントロールが出来る新生500シリーズをリリース希望。
糸フケが出易い釣り、例えばエギング用、特にナイトフィッシングには最適の一台となると思うのだが。
関連記事リンク
2015/03/14
Posted by KAZU@ at 10:10│Comments(2)
│釣:リール
この記事へのコメント
こんばんわ、トリガースピンの愛好家です。ご存知かもしれませんが、500系の後継の700系が日本の裏側にあります。
www.abugarcia.fr
→catalogue
→moulinets
を見てみてください。(このコメント欄はURL貼れないみたいなんですいません。)
Abumatic Premier 706、カッコは、506より不細工ですけどね。
まだ、絶滅危惧種、ということでw
www.abugarcia.fr
→catalogue
→moulinets
を見てみてください。(このコメント欄はURL貼れないみたいなんですいません。)
Abumatic Premier 706、カッコは、506より不細工ですけどね。
まだ、絶滅危惧種、ということでw
Posted by mega at 2010年05月19日 02:01
mega さん、こんにちは。
リンク先拝見しました。
ちょっと前まで売っていた704は知っていたのですが、NEW!706!!!
カベラスとBPSの春の新製品には無かったみたいですが、今後国内にも出回りますかね?
貴重な情報、ありがとうございました。
リンク先拝見しました。
ちょっと前まで売っていた704は知っていたのですが、NEW!706!!!
カベラスとBPSの春の新製品には無かったみたいですが、今後国内にも出回りますかね?
貴重な情報、ありがとうございました。
Posted by KAZU@ at 2010年05月19日 18:37
at 2010年05月19日 18:37
 at 2010年05月19日 18:37
at 2010年05月19日 18:37※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |