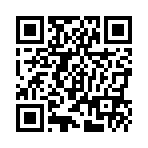2012年02月18日
ラパラ CD9
今回のお題はミノープラグの代名詞。

ラパラです。

メップスと並び、世界で最も有名なルアーでしょう。
古いのを数本、タックルBOXから引っ張り出してきました。
70年代に購入した物だと思います。
オレンジ/金のCD9が一番古い奴。

以前に紹介したインビシブルと一緒に買って貰った物で、かれこれ40年前のルアーです。
関連記事リンク
当時のラパラはヘドンやアーボガストより高価だったんじゃなかったかな?
小学生(当時)の小遣い、2~3カ月分の高価な玩具でした。
衝撃に弱いバルサボディー。
根掛かりし易いシンキングプラグ。
ビビりの私としてはロストが怖くて、中々使う勇気が無く、使用頻度が低かった。
結果として現在も残っています。
フォイルの輝きが一部無くなっていますが、これは剥がれたのでは無く、クリアーの下の箔の部分が変質して透明になった為。

CD9のもっとも一般的な使い方と言ったら、やはりスズキ釣りでしょう。
以前にもブログに書いたかも知れないけれど、私は狙ってスズキを釣った事が無いんですよね。
バスやトラウト狙いには使い辛いと言うのも使用する機会が少なかった原因かな?
多分、フローティングの赤金が無かったのでカウントダウンを買って貰ったのでないかと思うのですが、フローティングを買って貰っていたらとっくに津久井湖か相模湖の藻屑となっていたでしょう。
当時のラパラはツネミが輸入していました。
ガルシア(アメリカ)・ミッチェル(フランス)のロッドやリール。
ラパラ(フィンランド)/メップス・ルブレックス(フランス)/ダーデブル・ボーマー・フレッドアーボガスト(アメリカ)/ステイングシルダ(ノルウェー)等の舶来ルアーの数々が綺羅星の如く輝いていた、当時のツネミのカタログをボロボロになるまで繰り返し眺めていたのを思い出します。
カタログにはラパラCDのレントゲン写真がありましたね。
あの写真を見てプラグ作りを始めた方もいるのではないかと思います。
背中の赤は艶がありませんが、別にクリアーが剥げた訳では無く、元々艶消しでした。
白いテープの腹。

以前御紹介したバンゴーミノーも同構造です。
関連記事リンク
ワイヤーを埋め込んだ跡を隠す目的でしょう。
への字に描かれた赤い口。

リップの一部が削られています。

完成品を出荷前に一つ一つスイムテストをして、バランスが悪い場合は手作業でリップを削っているとカタログに書かれていました。
このF7は正面から見るとかなりリップが曲がっています。

当時は手作りに近い生産方式だったんですかね。
スイムテストが必要なのが良く判ります。

昔は眼も手書きだったのか、位置や大きさが左右でバラバラでしたが、90年代になってから構造も変わり、眼の大きさも揃う様になりました。

ジョイントラパラが追加されたのは70年代の終わり頃だったですかね?

単純にフローティングのボディーを分割したのでは無い、アクションに拘って作り込みがされていました。

こいつもリップの左側が結構削られています。

おちょぼ口。

その昔、ラパラは沢山釣れる事から『生き餌』呼ばわりされていて、使っているのは素人・・・的な扱いだった訳ですが、現在のスーパーナチュラル仕上げの国産ミノーと比較すると時代の流れを感じますねぇ。

昨年、開高健記念館に行ってから手持ちの巨匠の書籍を再読していたのですが、『ALL WAYS』に収録されている『視野の先住者たち』の一説にラパラの話が載っている。
関連記事リンク
要約すると、ラパラと言うルアーは偉大だが、偉大なのはラウリ・ラパラ氏であって釣り人では無い・・・銀山湖での話として、ラパラで釣りをしていた時にトビがラパラを小魚と間違えて襲いかかったがラインが絡んで捕獲された事が記載されている。
これは1985年2月に記された文だが、同じ様な話が以前御紹介した『ブラックバス釣りの楽しみ方』(1978年7月)にも載っている。
関連記事リンク
もっともルアーはラパラでは無く、スィンフィンシルバーシャッド&シャイナーミノーの紹介文に、場所は明記されていないがやはりプラグがトビに襲われる話が出てきます。
関連記事リンク
則氏と開高氏は銀山湖で面識が有った様なので、あるいは元ネタが同じなのかも知れません。
昨年30年振りに渓流の管理釣り場に行ったのですが、ラパラのF3を投げても見向きもしない魚が、ブラウニーの5cmで表層をトィッチしたら川底からワラワラと浮かんで来ました。
関連記事リンク
開高氏が存命で今のジャパンハイテクミノーを見たら何と表現するだろう?

ラパラです。

メップスと並び、世界で最も有名なルアーでしょう。
古いのを数本、タックルBOXから引っ張り出してきました。
70年代に購入した物だと思います。
オレンジ/金のCD9が一番古い奴。

以前に紹介したインビシブルと一緒に買って貰った物で、かれこれ40年前のルアーです。
関連記事リンク
2010/06/12
当時のラパラはヘドンやアーボガストより高価だったんじゃなかったかな?
小学生(当時)の小遣い、2~3カ月分の高価な玩具でした。
衝撃に弱いバルサボディー。
根掛かりし易いシンキングプラグ。
ビビりの私としてはロストが怖くて、中々使う勇気が無く、使用頻度が低かった。
結果として現在も残っています。
フォイルの輝きが一部無くなっていますが、これは剥がれたのでは無く、クリアーの下の箔の部分が変質して透明になった為。

CD9のもっとも一般的な使い方と言ったら、やはりスズキ釣りでしょう。
以前にもブログに書いたかも知れないけれど、私は狙ってスズキを釣った事が無いんですよね。
バスやトラウト狙いには使い辛いと言うのも使用する機会が少なかった原因かな?
多分、フローティングの赤金が無かったのでカウントダウンを買って貰ったのでないかと思うのですが、フローティングを買って貰っていたらとっくに津久井湖か相模湖の藻屑となっていたでしょう。
当時のラパラはツネミが輸入していました。
ガルシア(アメリカ)・ミッチェル(フランス)のロッドやリール。
ラパラ(フィンランド)/メップス・ルブレックス(フランス)/ダーデブル・ボーマー・フレッドアーボガスト(アメリカ)/ステイングシルダ(ノルウェー)等の舶来ルアーの数々が綺羅星の如く輝いていた、当時のツネミのカタログをボロボロになるまで繰り返し眺めていたのを思い出します。
カタログにはラパラCDのレントゲン写真がありましたね。
あの写真を見てプラグ作りを始めた方もいるのではないかと思います。
背中の赤は艶がありませんが、別にクリアーが剥げた訳では無く、元々艶消しでした。
白いテープの腹。

以前御紹介したバンゴーミノーも同構造です。
関連記事リンク
2008/12/23
ワイヤーを埋め込んだ跡を隠す目的でしょう。
への字に描かれた赤い口。

リップの一部が削られています。

完成品を出荷前に一つ一つスイムテストをして、バランスが悪い場合は手作業でリップを削っているとカタログに書かれていました。
このF7は正面から見るとかなりリップが曲がっています。

当時は手作りに近い生産方式だったんですかね。
スイムテストが必要なのが良く判ります。

昔は眼も手書きだったのか、位置や大きさが左右でバラバラでしたが、90年代になってから構造も変わり、眼の大きさも揃う様になりました。

ジョイントラパラが追加されたのは70年代の終わり頃だったですかね?

単純にフローティングのボディーを分割したのでは無い、アクションに拘って作り込みがされていました。

こいつもリップの左側が結構削られています。

おちょぼ口。

その昔、ラパラは沢山釣れる事から『生き餌』呼ばわりされていて、使っているのは素人・・・的な扱いだった訳ですが、現在のスーパーナチュラル仕上げの国産ミノーと比較すると時代の流れを感じますねぇ。

昨年、開高健記念館に行ってから手持ちの巨匠の書籍を再読していたのですが、『ALL WAYS』に収録されている『視野の先住者たち』の一説にラパラの話が載っている。
関連記事リンク
2011/09/25
要約すると、ラパラと言うルアーは偉大だが、偉大なのはラウリ・ラパラ氏であって釣り人では無い・・・銀山湖での話として、ラパラで釣りをしていた時にトビがラパラを小魚と間違えて襲いかかったがラインが絡んで捕獲された事が記載されている。
これは1985年2月に記された文だが、同じ様な話が以前御紹介した『ブラックバス釣りの楽しみ方』(1978年7月)にも載っている。
関連記事リンク
2009/01/01
もっともルアーはラパラでは無く、スィンフィンシルバーシャッド&シャイナーミノーの紹介文に、場所は明記されていないがやはりプラグがトビに襲われる話が出てきます。
関連記事リンク
2009/01/12
則氏と開高氏は銀山湖で面識が有った様なので、あるいは元ネタが同じなのかも知れません。
昨年30年振りに渓流の管理釣り場に行ったのですが、ラパラのF3を投げても見向きもしない魚が、ブラウニーの5cmで表層をトィッチしたら川底からワラワラと浮かんで来ました。
関連記事リンク
2010/10/23
開高氏が存命で今のジャパンハイテクミノーを見たら何と表現するだろう?
Posted by KAZU@ at 10:10│Comments(0)
│釣:ルアー
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。