2009年03月28日
ヘドン(HEDDON) トピード(トーピード:TORPEDO)
バスをトップで釣りに行くのに、一つだけプラグを持って行くとしたら何を持って行くか?

私の場合は間違い無くマグナムトピードです。

ペンシルベイト+スイッシャーって構造のプラグなので、ピンポイントではペンシルベイト、広範囲に探る時にはスイッシャー。
静水ではゆっくりと、荒れた水面では騒々しくバスを誘う。

汎用性の高さって言う点ではトピードを超えるプラグってあんまり無いと思う訳ですよ。
どんな状況、ポイントでも使えると言う利点を活かしてパイロットルアーとして使う事が多い。
もっとも器用貧乏って言うか、どんな状態でも使えるって言う事は、逆に言えばどんな状態でも中途半端と言う事になるので、風が強くて波立っている時にはスパターバグの方が良い気がするし、油を流したようなベタ凪の夕方だったらやっぱりザラを使いたくなる。
関連記事リンク:フレッドアーボガスト スパターバグ
関連記事リンク:へドン(HEDDON)オリジナルザラスプーク
毎回使うけれど使用時間自体は結構短い・・・そんなルアーです。
最初に買ったのが残っているが、これは70年代末位に購入したのだったか?

関連記事リンク:ABU アンバサダー5600C

写真の場所は霞ヶ浦。
90年代中頃かな?
この頃は毎週フロートチューブで浮いていた。
関連記事リンク:STILLWATER SARATOGA
この後、バスが網で大量に捕獲されて河口湖に売られたり、アメリカナマズの大繁殖とかが原因だと思うけれどバスの絶対量が減少。
こっちは90年代に購入した物。

関連記事リンク:ABU アンバサダー 4600C クラッシック
関連記事リンク:フェンウイックHMG GC555

写真の場所は八郎潟。
2000年代に入ってから、昔の霞の爆釣が忘れられなくて東京から車を走らせて年に数回通っていました。
あまり大型は釣れなかったけれど、やはりトップでバコバコ釣れるとなれば半分徹夜のドライブも苦にならない。
ちなみに数年前に八郎潟はリリース禁止となり、それ以降一度も行っていません。
まあ、みんな知っていると思うけれど、八郎潟は昔は自然の湖だった訳ですよ。
それを大規模集約農業の為に干拓して埋め立ててしまった。
今の残存湖は、言い方は悪いかも知れないけれど人工の田んぼの用水路と同じでしょ?
そんな場所で今更在来魚の保護って・・・しかも方法がリリース禁止って・・・
全く手付かずの自然湖で、そこにしか生息していない貴重な固有種を保護する為にバス駆除って言うなら私も賛成。
現実問題としてそんな自然湖は北海道の極一部にしか無いと思うけれど。
八郎潟は人間が散々手を入れて管理している場所なんだから積極的にバス釣りを誘致しても良い位だと思うのだが。
八郎潟周辺は整備の行き届いた居心地の良いキャンプ場が幾つもあるし、私の好きな温泉が周囲に点在しているし、海も近くて食べる物も美味しいしで大のお気に入りスポットだっただけに残念だ。
ちなみにリリース禁止になってから、琵琶湖も行っていない。
今でも時々、八郎潟や琵琶湖に行ってみたくなる事がある。
しかし、確かに無意味な規制だとは思うけれど、リリースしちゃ駄目だって言うなら何年先になるかは判らないけれど規制が解除される迄は行くのは止めて置く。
もう30年も前の事だけど、確か静岡県だったか、内水面のルアーフィッシングを全面禁止していた事があったはずだ。
バス釣り禁止じゃあ無いよ。
ルアーで何を釣っても駄目って話。
今ではとても考えられない事だけど、アユの友釣りにプラグを使って引っ掛け釣りをする人がいるから駄目って理由だったように記憶している。
今も売っているかどうかは知らないけれど、当時は鮎の友釣り用プラグなんて奇妙な物も実際に売っていたんですよ。
生きているおとり鮎の代わりにフローティングのミノー(鮎カラー)を付けて、リール竿じゃあ無くて鮎竿で友釣りする方法。
ラパラに板鉛を張り付けて自作する方法が釣り雑誌にも載っていたような・・・
渓流の本流筋で鮎が生息している所でミノーを投げた事が有る人は判ると思うけれど、鮎は縄張りに近付くルアーにもアタックして来るよね。
別にコロガシ釣りをやってる訳では無くて、オトリが生きているかプラグかの違いだけなんだけれど、ルアーのフックが3本針なんで、3本バリ=ギャング釣りだと思い込んだ人がいたのだろう。
流石に現在そんな事を言う人はいないよね。
何十年か先の釣り人は、バスのリリース禁止条例なんてあったと聞いても信じないかも知れない。
現在琵琶湖や八郎潟でバス釣りしている人は、バスを釣ったらせめて美味しく食べてあげて下さい。
土に埋められたり、肥料にされたりじゃあバスも成仏出来ないだろう。
今回も話が随分横道にそれたな。
話をトピードに戻す。
ぱっと見、ペラの形状が違うけれどアクションなんかは殆ど同じ。

クリアー持っていないので内部構造の違いは判らないけれど
外観

腹周り

フックも全く同じに見える。

30年間全く不変・・・それだけ完成度が高いと言う事か。

しかし、改めて眺めて見ても、全く無駄の無いデザイン・・・以前は後部のペラを取ってウエイトかましてペンシルに改造したり、ワイヤーガード付きのシングルフックを付けてリリィパッド用に改造した事もある。

しかし、何か付けても、何処かを削ってもバランスが崩れてトピードとはかけ離れた物になってしまう。
おそらくこいつも30年後に、今と全く同じ物が釣り具店の店先に並んでいるに違いない。


私の場合は間違い無くマグナムトピードです。

ペンシルベイト+スイッシャーって構造のプラグなので、ピンポイントではペンシルベイト、広範囲に探る時にはスイッシャー。
静水ではゆっくりと、荒れた水面では騒々しくバスを誘う。

汎用性の高さって言う点ではトピードを超えるプラグってあんまり無いと思う訳ですよ。
どんな状況、ポイントでも使えると言う利点を活かしてパイロットルアーとして使う事が多い。
もっとも器用貧乏って言うか、どんな状態でも使えるって言う事は、逆に言えばどんな状態でも中途半端と言う事になるので、風が強くて波立っている時にはスパターバグの方が良い気がするし、油を流したようなベタ凪の夕方だったらやっぱりザラを使いたくなる。
関連記事リンク:フレッドアーボガスト スパターバグ
関連記事リンク:へドン(HEDDON)オリジナルザラスプーク
毎回使うけれど使用時間自体は結構短い・・・そんなルアーです。
最初に買ったのが残っているが、これは70年代末位に購入したのだったか?

関連記事リンク:ABU アンバサダー5600C

写真の場所は霞ヶ浦。
90年代中頃かな?
この頃は毎週フロートチューブで浮いていた。
関連記事リンク:STILLWATER SARATOGA
この後、バスが網で大量に捕獲されて河口湖に売られたり、アメリカナマズの大繁殖とかが原因だと思うけれどバスの絶対量が減少。
こっちは90年代に購入した物。

関連記事リンク:ABU アンバサダー 4600C クラッシック
関連記事リンク:フェンウイックHMG GC555

写真の場所は八郎潟。
2000年代に入ってから、昔の霞の爆釣が忘れられなくて東京から車を走らせて年に数回通っていました。
あまり大型は釣れなかったけれど、やはりトップでバコバコ釣れるとなれば半分徹夜のドライブも苦にならない。
ちなみに数年前に八郎潟はリリース禁止となり、それ以降一度も行っていません。
まあ、みんな知っていると思うけれど、八郎潟は昔は自然の湖だった訳ですよ。
それを大規模集約農業の為に干拓して埋め立ててしまった。
今の残存湖は、言い方は悪いかも知れないけれど人工の田んぼの用水路と同じでしょ?
そんな場所で今更在来魚の保護って・・・しかも方法がリリース禁止って・・・
全く手付かずの自然湖で、そこにしか生息していない貴重な固有種を保護する為にバス駆除って言うなら私も賛成。
現実問題としてそんな自然湖は北海道の極一部にしか無いと思うけれど。
八郎潟は人間が散々手を入れて管理している場所なんだから積極的にバス釣りを誘致しても良い位だと思うのだが。
八郎潟周辺は整備の行き届いた居心地の良いキャンプ場が幾つもあるし、私の好きな温泉が周囲に点在しているし、海も近くて食べる物も美味しいしで大のお気に入りスポットだっただけに残念だ。
ちなみにリリース禁止になってから、琵琶湖も行っていない。
今でも時々、八郎潟や琵琶湖に行ってみたくなる事がある。
しかし、確かに無意味な規制だとは思うけれど、リリースしちゃ駄目だって言うなら何年先になるかは判らないけれど規制が解除される迄は行くのは止めて置く。
もう30年も前の事だけど、確か静岡県だったか、内水面のルアーフィッシングを全面禁止していた事があったはずだ。
バス釣り禁止じゃあ無いよ。
ルアーで何を釣っても駄目って話。
今ではとても考えられない事だけど、アユの友釣りにプラグを使って引っ掛け釣りをする人がいるから駄目って理由だったように記憶している。
今も売っているかどうかは知らないけれど、当時は鮎の友釣り用プラグなんて奇妙な物も実際に売っていたんですよ。
生きているおとり鮎の代わりにフローティングのミノー(鮎カラー)を付けて、リール竿じゃあ無くて鮎竿で友釣りする方法。
ラパラに板鉛を張り付けて自作する方法が釣り雑誌にも載っていたような・・・
渓流の本流筋で鮎が生息している所でミノーを投げた事が有る人は判ると思うけれど、鮎は縄張りに近付くルアーにもアタックして来るよね。
別にコロガシ釣りをやってる訳では無くて、オトリが生きているかプラグかの違いだけなんだけれど、ルアーのフックが3本針なんで、3本バリ=ギャング釣りだと思い込んだ人がいたのだろう。
流石に現在そんな事を言う人はいないよね。
何十年か先の釣り人は、バスのリリース禁止条例なんてあったと聞いても信じないかも知れない。
現在琵琶湖や八郎潟でバス釣りしている人は、バスを釣ったらせめて美味しく食べてあげて下さい。
土に埋められたり、肥料にされたりじゃあバスも成仏出来ないだろう。
今回も話が随分横道にそれたな。
話をトピードに戻す。
ぱっと見、ペラの形状が違うけれどアクションなんかは殆ど同じ。

クリアー持っていないので内部構造の違いは判らないけれど
外観

腹周り

フックも全く同じに見える。

30年間全く不変・・・それだけ完成度が高いと言う事か。

しかし、改めて眺めて見ても、全く無駄の無いデザイン・・・以前は後部のペラを取ってウエイトかましてペンシルに改造したり、ワイヤーガード付きのシングルフックを付けてリリィパッド用に改造した事もある。

しかし、何か付けても、何処かを削ってもバランスが崩れてトピードとはかけ離れた物になってしまう。
おそらくこいつも30年後に、今と全く同じ物が釣り具店の店先に並んでいるに違いない。

Posted by KAZU@ at 10:10│Comments(0)
│釣:ルアー
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。




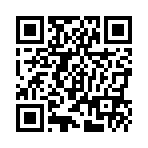




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17454745.10bfafe3.17454746.f40d967c/?me_id=1243733&item_id=10000652&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjisso%2Fcabinet%2Fheddon_torpedo.gif%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjisso%2Fcabinet%2Fheddon_torpedo.gif%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)










